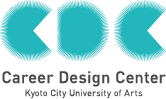野中亜紀(エジプト学者・音楽学者)
博士(国際関係学)。岐阜県岐阜市出身。 愛知県立芸術大学音楽学部音楽学コース卒業、京都市立芸術大学大学院音楽学専攻修了。 専門は、古代エジプト音楽。エジプト学を中野智章氏に師事。 中部大学サテライトカレッジ「古代エジプト史」講師、尾張旭市成人大学「古代エジプト史」講師を務める。 現在、愛知文教大学サテライトカレッジ「古代エジプト史」「クラシック音楽講座」講師、 愛知文教大学、愛知文教女子短期大学非常勤講師。愛知県立佐屋高等学校音楽科非常勤講師。 エジプト・コレクション展覧会およびナショナルジオグラフィック番組を監修。クラシック音楽CDの曲目解説、演奏会での曲目解説、全国でレクチャーコンサート等のMC、シニア公開講座等で講演を行っている。著作『ツタンカーメン王墓出土の楽器ーエジプト学と音楽学のはざまでー』
インタビュー:柳楽正人(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター音楽アドバイザー)
→ 前編はこちら
■愛知に誕生したクラシック講座 ―現在はエジプト関連の講座だけじゃなくてクラシック講座もされてますが、それはどういうきっかけで始まったんですか? 野中:博士時代から中部大学のサテライトカレッジでエジプト講座をやってたんですけど、それが建物の老朽化でなくなるという話になったんです。それを非常勤で行っていた愛知文教大学の学長にお話ししたところ、じゃあうちでやらない?って言ってくださったんです。エジプト以外に何かある?と聞かれたので、やってみたい講座があるんですと言ってクラシック音楽講座が誕生しました。 それを思いついたのは、京芸にいたからなんですよ。京芸にいた時に弥生ちゃんの伝手で、音楽学者の近藤秀樹先生がされているクラシック講座に出させていただいたんです。シニアの方もたくさん受講されているし、演奏と融合していて学生さんにも出番がある。すごくいいなと思ったんですよ。京芸に行かなかったら講座に出させてもらうこともなかったし、多分こんな講座があるんなんて全然気づかなかった。 でも思えば苦労の連続でしたね。今4年目で何となく軌道に乗っていますけど、最初は授業の仕方もわからないし、愛知にこういう講座がなかったから、受講者が来るのかもわからない。最初は10人もいませんでした。本当に継続は力なりだと思います。1年ちょっとで辛いなと思う時もあったし、SNSで炎上して嫌な思いもしました。でもここで辞めたら「だから辞めたんだ」って言われるじゃないですか。それだけは絶対に嫌だと思って。負けん気ですよね。

―きっと根本的に野中さんはタフなんですね。そもそも文教大学の非常勤というのは、どういう経緯で行かれてたんですか? 野中:本当に偶然なんですよ。中学校で産休されていた先生が、愛知文教大学の入学式でピアノを弾いておられたんです。アルバイトというかピンポイントで入学式だけ行かれていて。でも産休に入ったから代わりに行ってもらえますかと言われたんです。それがきっかけで、授業も担当させていただけることになりました。 ―全部が奇跡的なタイミングで繋がっているんですね。 野中:タイミングが奇跡ですよね。中学校にその産休の先生がいなかったら、私は中学校にも教えに行ってなかったし、文教にも行ってなかったです。正直、入学式のピアノ演奏は金額としては微妙だったから、もしかしたらピアノ科の人だったら引き受けなかったかもしれない。どんなところから仕事が転がり込むか本当にわからないですね。

入学式や卒業式は演奏が入ります
たくさんの経験をさせてくださる学長に感謝
―エジプトの話に戻りますが、将来こうなりたいという夢はあったんですか? 野中:県芸に入った時は、とにかく古代エジプトの音楽を知りたいという気持ちだったから、特に将来の夢というのはなかったです。明確に考え始めたのは大学院の時でした。「私、まだ途中じゃん」って。やっと貴族の音楽の様子がわかっただけで、まだ全然ラムセスに近づけてないと思ったんです。 博士に入った時に先生から、あなたはどうなりたいの?って言われたんです。大学の先生にはなりたいと思ってもなれないよ、それでも大丈夫?ということを結構はっきりと言われました。これからどんどん少子化になるから、昔みたいにずっとひとつの研究だけをしてたらだめだよって。エジプトもできて音楽もできるというから僕はあなたを引き受けた、エジプトだけをやりたいと言っていたら最初から断ったと言われました。エジプトだけやって博士号を持っていても先生になれない人はたくさんいるから、道を見つけるためには音楽と社会の両方をできるようになりなさいと言われました。人文学とか歴史は最初に削られていく学科だけど、教育学の音楽は絶対に残る、音楽には道があるという言い方をされていましたね。 今は大学の先生でも淘汰される時代です。昔なら授業で学生が寝ていて先生がひとりで喋っていても「でもすごい先生なんだよ」で終わってたんですけど、最近は授業がだめだとクビもある時代になってきました。その点では中学校の教員をやっておいてよかったなと思いますね。中学校は他の先生が授業を見に来られたり、研究授業を絶対にやらないといけないので、他の先生に指摘されたりして自分も成長できる。でも大学はそれがないんですよ。学生のアンケートはあるけど、それで直る先生はそもそもそんな変な授業はしていないので。中学校の教員になる時は、周りから「もう研究は辞めたんだ」みたいなことも色々言われたし、自分自身悩んだ時でもあるんですけど、でも今はやってよかったですね。

―中学校で教えていた2年間は、研究という意味ではほぼストップしてたんですか? 野中:ストップでした。時間がなかったので。土日も部活でしたし。 ―そんな荒れた学校でも部活があるんですね。 野中:そうなんですよ。合唱部はなくて吹奏楽部だったんですけど、文化系のやんちゃな子が集まっていました。めちゃくちゃ荒れている子たちは運動部に行けるんですけど、そこまでの元気がない荒れた子が来ていて吹奏楽部も大変でした。親のクレームもすごかったです。「なんで平日は7時半からやってるのに土日は9時からなんですか」とか。お母さんは働きに行きたいから、その時間に家にいられると困るわけですよ。でも私にもプライベートがあるし、先生を何だと思ってるんだろうと思っていました。だから私は部活反対論者、廃止論者です。どの教育論文でも部活はいらないと書いてます。
■音楽教育の現場で感じた問題点 ―教育論文を書かれているんですか? 野中:最近、保育士の資格を取ったんですよ。それで幼稚園の現場にも行けるようにしたんです。一貫した音楽教育が重要だと思っているので。今は高校に教えに行っているんですよ。どうしても高校に行きたくてお願いして、高校の音楽も担当させてもらっています。これで小、中、高校、大学とフルコンプです。全部一貫した現場を見たかったんです。 ―どういうきっかけで一貫した音楽教育の必要性を考えるようになったんですか? 野中:一番は中学校で教えてから小学校に行った時に、全然繋がってないと思ったことです。さらに小学校と幼稚園も分離されている。そうすると全く違う音楽をやるんですよ。今、幼稚園は個が大事なんですね。だからみんなで一緒に合奏するというよりかは、その子がやりたい音楽をやらせるという、個の音楽教育にシフトしていってるんです。でも小学校に入ると逆になるんですよ。みんな一緒に歌いましょうになるから、逆行してるんですよね。 中学校はちゃんと教科書を使おうとか、色々と言いたいことはあるんです。私が行ってた中学校は音楽の教科書を全然使わないから、何やってるんだろうと思ってたんです。それで他の学校の先生に「教科書やってます?」って聞いてみたら、やってないんですよ。これはだめでしょと思って。 あとは、国際化で海外の人と話す時に自分の国の音楽を全く知らないのは問題だろうという考えから、まず日本の音楽をやるという方向になってきています。でもその分、西洋音楽は削られていくんですよ。そうすると全く楽器に触れ合わないから、フルートを鉄の棒だと思う子が出たりとかするんです。そもそも中学校の先生は尺八を吹けないし、能とかを中学生に理解させるのは難しいですよ。大学生でも難しいですもん。もっと鑑賞の時間を増やしてとかちゃんと教科書を使おうとか、現場の中で色々と言いたいことはあります。

―そもそも野中さんにとって中学校の先生という仕事は、期間限定のお金を稼ぐ手段という程度でやり過ごすこともできたわけですよね。本来やりたいことはミイラなんだから。それが最終的には教育論文を書こうと思うくらいまでになったというのは、野中さんの中にある責任感からくるものなんですかね。 野中:母親が教員だったのはあるかもしれないですね。おばあちゃんも小学校の教員だったので、教員家庭という血筋はあるかもしれません。 ―大学で教員免許を取ったのはなぜなんですか?教員免許があってよかったと思えるのは、もうちょっと後になってからじゃないですか。当時は保険で押さえておこうみたいな感じだったんですか? 野中:それが、もっと打算的なんです。せっかく学費を払うなら取っておいたほうがいいじゃんってことですよ。免許を取るのにお金は変わらないから。だから学芸員も取りました。学芸員を取った人は音楽学部ではもうひとりぐらいしかいなかったんですけど。だって全部取らないと損じゃんって(笑)。 ―でも結果、それがすごく役に立ってますよね。 野中:そうですよ。学芸員の資格がないと展示会のお仕事ができない時もありますし。学芸員も取っておいて本当によかったです。最初は打算だったけどいつか役に立ったりするから。何が役に立つかはその時にはわからない。

自分が監修側に回ることができるようになるとは
この時は夢にも思っていませんでした
■博士号を取ると見える世界が変わる ―音楽学部は実技系の人が多いから、学者としての道を進む人のイメージがあんまりできなかったんですが、お話しを聞けてよかったです。 野中:「どうやって食べていくんだ」みたいな言葉を投げかけられることは、体感100回くらいあったので、それをどう乗り越えるかというのも重要ですね。本当にしょっちゅう言われました。私の場合は女性というのもあります。エジプト学者は男性が圧倒的に多いし、認知されてるのも男性なんですよね。もちろん学会に女性はいらっしゃるけどメディアには出てこない先生が多いし、やっぱり少ないんですよ。だからエジプトを研究していると言っても信じてもらえなかったです。しかも10代の間はエジプトにも行けていなかったから。今は「エジプトでどうやって食べていくの?」って言われたら「最近ちょっと食べ過ぎて太りましたけどね」って絶対に言うと思う(笑)。

博士号を取るのに6年かかりました。すごく辛かったですね。論文を2本出さないと博士に申請できないけど、出せる学会もすごく少ない。とにかくどこかに論文が2本乗らないといけないので、若手が出せそうなところに出してみたりして、それが結構大変でしたね。何回泣いたかなっていうぐらい泣きました。家族をはじめ、この道に進むことを許してくれる周りがあったから来れたのはありますね。だって中学校の先生をずっとやってた方がいいっていう人も絶対いるだろうし。子供を音大に行かせる親御さんなら「あなたの好きなことやりなさい」という方が多いと思うけど、それにしてもこんなに長くたくさんやらせてもらえたので。 「博士号を取ると見える世界が変わるよ」と言われていたんですけど、本当にその通りだなと思っています。博士号を取る前は「知ってる?ピラミッドってさ、奴隷が作ったんじゃないんだよ」とか色々と説明してくる人もいたんですけど、博士を取ったら一切なくなったんですよ。メディアの仕事とか辞典の仕事とか、いただけるお仕事も変わりますし。なおかつ書籍を出版するとまた世界が変わりました。
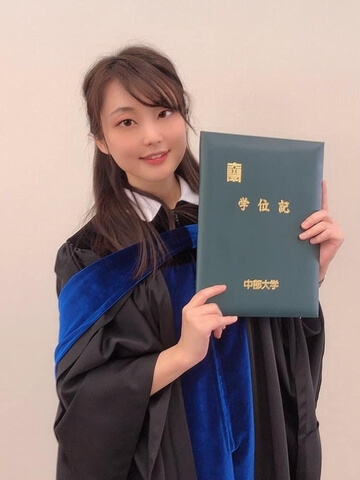
―エジプトに興味を持ったそもそものきっかけはラムセス1世だったんですが、そのラムセス1世には近づけているんでしょうか。 野中:大分近づけています。ツタンカーメン王の楽器までいったので。でもラムセス1世は治世が短かかったから、現状はここら辺がマックスなのかなという気もします。 ―最近ではYouTubeでの講座がはじまったりしていますが、これから活動の幅がどんどん広がっていきそうですね。 野中:来年、新しい音楽辞典が出るんですけど、そこでエジプト音楽の項目を書けたので、先生にお送りしようと思ってます。先生のおかげです、ありがとうございますって。 博士の時は「何だこの論文は?」って先生にたびたび叱られていたんですよ。演奏の仕事を引き受けすぎると、あなたは何がしたいの?って言われました。「私はあなたを、古代エジプト音楽と言ったらあなたに聞けという人間になってほしくて引き受けたんです。あなたを音楽家にするためじゃない。それをゆめゆめ忘れないようにしてください」って。だから先生は演奏の仕事を一度も見に来られたことがないですし、博士を取るまでは行かないとずっとおっしゃってましたね。音楽辞典をお送りして、ちょっと先生に恩返しできるかなと思っています。 あとは音楽学の研究材料が自分の中であるから、それをちゃんと形にして発表しなきゃなというのはずっと思っています。大学教員をやるとやっぱり忙しくて学会発表とかをやらなくなっちゃうので、ちゃんと業績を積んでいきたいです。クラシック音楽の講座ももっともっと広げていきたいし。ありがたいことに大垣とか美濃加茂からも講座のお話をいただいています。やりたいことがたくさんですね。 ―クラシック音楽もエジプトも音楽教育も、どれも太く長く枝葉を広げての益々のご活躍をお祈りしています。今日は貴重なお話をありがとうございました!

野中ゼミのメンバー

<野中さんの著書> 『ツタンカーメン王墓出土の楽器: エジプト学と音楽学のはざまで』 ●著者 野中亜紀 ●定価 3,300円(本体3,000円+税) ●発行 2023/7/31 ●出版 株式会社みらい 古代エジプトの音楽とはどのようなものだったのか。 100年前に発見された古代エジプト第18王朝ツタンカーメン王墓から出土したクラッパー、シストラム、トランペットの3種類の楽器。 これらの楽器に残されたヒエログリフや音楽場面が描かれた図像から、古代エジプトの時代背景とともに、ツタンカーメンが生きたアマルナ時代の音楽を探り、古代ギリシアがルーツといわれる西洋音楽と古代エジプトの音楽とのつながりをも解き明かした著者渾身の一冊。 → 株式会社みらいのページ → Amazonのページ

<野中さんの出演動画> エジプト考古学者、河江肖剰さんのYouTubeチャンネル「河江肖剰の古代エジプト」に出演されています。 (2024年9月現在の出演動画) ●【特別企画】3千年の歴史が紡ぐ旋律~古代エジプト音楽の秘密(2023/05/13) ●【伝説のカップル】ユリウス・カエサル~クレオパトラに愛された男の真実(2024/07/27) ●【解説】エジプト滅亡~クレオパトラとアントニウスの悲劇的な結末(2024/08/17)