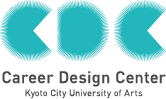野中亜紀(エジプト学者・音楽学者) 博士(国際関係学)。岐阜県岐阜市出身。 愛知県立芸術大学音楽学部音楽学コース卒業、京都市立芸術大学大学院音楽学専攻修了。 専門は、古代エジプト音楽。エジプト学を中野智章氏に師事。 中部大学サテライトカレッジ「古代エジプト史」講師、尾張旭市成人大学「古代エジプト史」講師を務める。 現在、愛知文教大学サテライトカレッジ「古代エジプト史」「クラシック音楽講座」講師、 愛知文教大学、愛知文教女子短期大学非常勤講師。愛知県立佐屋高等学校音楽科非常勤講師。 エジプト・コレクション展覧会およびナショナルジオグラフィック番組を監修。クラシック音楽CDの曲目解説、演奏会での曲目解説、全国でレクチャーコンサート等のMC、シニア公開講座等で講演を行っている。著作『ツタンカーメン王墓出土の楽器ーエジプト学と音楽学のはざまでー』
インタビュー:柳楽正人(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター音楽アドバイザー)
■エジプトとの出会い、そして愛知県芸へ ―野中さんは愛知県立芸術大学(以下「県芸」)の音楽学専攻で学ばれたんですよね。もともと大学に入る前は、ピアノをされていたんですか? 野中:3歳くらいからずっとピアノを習っていました。小学校の時は、何となくこのまま音楽の道で行くのかなとぼんやり思ってたんです。でも小学4年生か5年生くらいの時に「天は赤い河のほとり」という漫画を読んで、ヒッタイトに出会っちゃったんですよ。こんな面白い世界があるのかと思いました。でも当時ヒッタイト帝国は日本ではほとんど知られてなくて、日本語の文献もほとんどなかったんです。それでツタンカーメンが死んだ時に、ヒッタイトとエジプトが交わるエピソードがあったので、エジプトを調べてみようと思って調べてみたら、そこでラムセス1世と運命的な出会いを果たしたんです。こんなかっこいいミイラがいるなんて!と思って、中学校3年間はミイラとエジプトについて一生懸命調べました。 ―ラムセス1世のことを知るために、エジプトを調べることにしたんですね。 野中:好きな人のことを何でも知りたくなっちゃうじゃないですか。それが本当に楽しかったんですよ。あ、私これが好きなんだと思いました。その時に、ラムセスはどんな音楽を聴いてたんだろう?って思ったんです。 ―好きな男の子が聴いてる曲って何だろう、みたいな。 野中:それです。だから全然語れるような理由じゃないというか。それで古代エジプト音楽のことを調べてみたら、全然調査が進んでなかったんですよ。当時は代表的な研究者がひとりしかいなくて、フランス語の文献しかなかった。高校1年生の時、大学で古代エジプト音楽を調べるにはどうしたらいいか考えて、音楽学しかないと思いました。私には妹がいるので、親からは公立の大学しか無理だよと言われていて、必然的に県芸を目指しました。 多分、県芸の先生方にはヤバいやつが来たなと思われたと思います。「ピアノの製作について」という入試の小論文で、ピラミッドの作り方を説明したんです。アピールする場所が他になかったんですよ。小論文を経て面接だったから、小論文で少しでも触れないと、面接でいきなり言い出してもヤバいやつでしょ?「こんなこと書きましたけど、実はエジプト音楽の研究がしたいんです」って言っても、じゃあ先に書きなさいよってなるし。 ―いや、ならないでしょ!これはヤバいやつが来ましたね(笑) 野中:模範解答がいまいちわからなかったんですよ(笑)。それで面接に進んだ時に「ピラミッドは何で無くなっちゃったの?」って聞かれたんです。今なら答えられるんですけども、その時は答えられなかった。「まあでもいいか、やることが決まってた方がね。また会いましょう」みたいに言われて、奇跡的に入学できました。

どこにいるかは探してください笑
音楽学専攻はコンサートの曲目解説を書くことが大事な仕事なんですが、エジプトの歴史しか知らなかった私にとっては、最初はそれがすごく大変でした。先生には「エジプトにしか興味がないのはわかるんだけど、でもやらないとだめだからね」って言われて。そこで曲目解説の書き方とか、資料の調べ方とかを全部叩き込まれたので、それはすごくよかったと思っています。その時は役に立つと思わなかったですけどね。 ―本来自分がやりたいエジプト音楽とは関係ないですもんね。 野中:こんなのやってどうするんだろう?と思っていました。きっと当時の先生は、私が今クラシック講座をやってるって知ったらびっくりしちゃうと思う。当時の県芸の音楽学専攻は、定期演奏会では曲目解説を書くことくらいしかなかったんですが、なぜか私の代だけ、演奏会でステージに上って曲目解説をするというのがあって、私が音楽学の代表としてそこに選ばれたんです。そこで作曲の先生にインタビューしたり、曲についてわかるように説明したりしたんですが、その時に、こういうの好きだなって思いました。エジプトが好きだったから音楽の仕事なんて全く興味がなかったのに、面白いじゃんって思ったんです。地味な専攻だと思っていたのが、私の中で急に華やかな専攻に変わりました。今では定期演奏会でポスター発表などあるみたいですけどね。

(時代が出ていますね)
■京芸の修士課程で音楽学を研究 ―学部を卒業した後の進路としては、就職も視野に入れていたんですか? 野中:エジプトの勉強を続けるにはどうしたらいいかということだけでした。4年間、先行研究しか調べなかったから、私の研究はここからじゃん!と思って。でも大学4年生の時に「アラブの春」(*)が起きたんです。それで渡航禁止になってしまって、大学院に行ったとしても現地には行けなさそうだった。県芸の先生からは「どこに行ってもあなたがやっている研究をしてる人はいないんだから、県芸の院でいいんじゃないの?」と言われました。非常勤で来られていた先生に相談したら「京芸におられる民族学の龍村あや子先生なら、あなたの研究を面白いと思ってくれるんじゃない?」と言われました。それで龍村先生に会いに京都に行ったんです。先生は「私のところに来なさい。面倒を見るわ」と言ってくださいました。
* アラブの春:2010~2012年にかけてアラブ世界において発生した、大規模反政府デモを主とした騒乱。
こうして京芸の大学院を受けたんですが、西洋音楽史の点数がめちゃめちゃ悪かったんです。だから絶対に通らないと思っていたら、奇跡が起きて合格できたんです。私が今クラシック講座をやっていると知ったら、きっと龍村先生もびっくりしちゃう(笑)。 京都の生活は楽しかったですね。喫茶店のモーニングと味噌がないことだけがちょっと不安でした。京都に来た時に「喫茶店にモーニングがないじゃん!みんな朝ごはんはどこで食べてるの?」って言ったら「亜紀、落ち着いて。朝ごはんは家で食べるのよ」って(笑)。あと、おでんを食べようと思ったら味噌がない。「みんな何で食べてるの?」って聞いたら「え……出汁?」って(笑)。愛知は絶対に味噌がついてくるから、ここは味噌もない国なんだと思って、ここで暮らしていけるかなと思いました。 京芸は大変なことも多かったけど、県芸では体験できなかったことができました。龍村先生は民族音楽学者の小泉文夫先生の愛弟子だったので、アウトリーチの仕方とかを教えてくださったし、ドイツの博物館とかに連れていってくださって、いろいろと説明もしてくださって、現地を見ることができたのはすごくよかったです。先生からは、博士課程に来なさいと言われました。だけど別の先生からは「あなたは音楽学の基礎はできている。足りないのはエジプト学だ」と言われたんです。その時はどうしたらいいかわからなかったんですよね。結局、博士課程を受けたものの落ちちゃったんです。そのまま修了式を迎えて、一度路頭に迷ったんですよね。

■音楽教師として荒れた中学校に赴任 ―修士を取ってすんなりエジプトの研究に進まれたんだと思っていました。じゃあしばらくフリーター生活に入るわけですね。 野中:そうしたらある日、中学校から電話がかかってきました。教員免許を持っている人は卒業する際に講師登録をするんですが、それを見たある中学校の校長先生から電話がかかってきたんです。音楽の教員が産休でいないから来られませんかって。でも教員免許は資格として取っていただけなので、先生になる気なんて全然ありませんでした。 ―産休の先生の代理だから、とりあえずの期間限定なんじゃないんですか? 野中:2人目も産みたいから6年間はお願いしたいと言われました。最初から決まってるんだ?と思いましたけど。11月から来てほしいと言われたので、もし嫌だったら3月で辞めたらいいんじゃないのと周りに言われました。ある方からは「これからは子供の数が少ないから、音楽学で大学の先生になるのは超難しい。でも教育学部の音楽の先生は絶対に必要だから、そういう道に進もうと思った時に教員としての現場経験が絶対に必要になってくる。そこも視野に入れた方がいいんじゃないか」と言われたんです。それはすごく腑に落ちたんですよ。じゃあやってみようと思いました。 その中学校は「元気がいい」とは聞いてたけど、すごく荒れてたんです。本当に大変でしたね。普通は全校集会とかで新任の挨拶があるじゃないですか。それがなかったんです。すぐ辞めちゃうと思われていたみたいです。そもそも荒れすぎていて生徒を集められない。とりあえず職員室の前で先生方に挨拶をしていたら、急にひとりの先生が入ってきて「校門で生徒がタバコを吸ってます!」って。それで教頭先生に「じゃあ挨拶は終わりです。野中先生、行ってください」って言われたんです。結局その日のうちにタバコ事件と、給食のやかんにマヨネーズを入れる事件と万引きの3つの事件があって「野中先生はどの生徒指導に行きたいですか?」って言われて。その中なら……やかんですかね、みたいな(笑)。 ―タバコと万引きは普通に法を犯してますもんね(笑)。 野中:それくらいすごく大変だったんですよ。大荒れに荒れていて。前任の先生は6年経てばさすがに落ち着くだろうって思われてたのかな。音楽の授業が一番荒れるから。 ―音楽の授業はちゃんと生徒が教室にいるんですか? 野中:全然いないですよ。一番ヤバいクラスはひとりじゃできないから、他の先生にも来てもらっていました。暴れる生徒を他の先生が見ている横で私が授業をする、みたいな感じでした。荒れている学校で音楽の授業をやろうと思うと、必然的に授業が上手くならないとできないんですよね。体育みたいに叱りつけてやる教科でもないし、座っていれば過ぎる授業でもないから。音楽は人を動かさなきゃいけない。自分の授業自体がすごいレベルアップしたのは、この修行があったからです。今やっているサテライトカレッジもそうですが、大学でいきなり授業をやれと言われても多分できなかった。 ―すぐに辞めようとは思わなかったんですか? 野中:カルチャーショックが凄すぎて辞めようとも思わなかったです。ただ単に打たれ強かったというのもありますけどね。多分すぐに辞めちゃうだろうと思われてたけど、意外にメンタルが強かった。あとはこんな状況だから、私の代わりはもう来ないだろうなとも思いました。 ―メンタルの強さと責任感ですね。 野中:今思えば、本当に初めての先生にやらせる学校ではないです。多分ヤバい学校だということを知らないから、初めての私を狙って連絡してきたんですよ。母が教員だったから、色々とアドバイスをもらいました。母が教員だった時も荒れていた時代だったんですよ。「あの子たちは動いてるものに興味を持つから、まずビデオを見せて」とか言われました(笑)。そんなの大学では習わないじゃないですか。音楽の授業から荒れていくなんて多分みんな知らないし、現実を教えてあげた方がいいなと思いますね。 でもその荒れ果てた中学校で2年やった経験が、今すごく役に立ってます。博士論文を書くのも結構辛かったけど、この中学校での経験があったからこそ乗り越えられたっていうのはあったかもしれません。

吹奏楽部顧問をしてソロコンクール県大会にて
■中部大学の博士課程でエジプト学を研究 ―中学校の話が強烈でエジプトのことを忘れかけていました(笑)。ここから博士課程に行かれるんですよね? 野中:中学校で先生をして2年後に、私の博士課程のエジプト学の先生、中野智章先生が東京から中部大学に来られたんです。先生は県芸に考古学の非常勤として来られていたので、もともとそこで出会って「古代エジプトの音楽をやりたいんです」ということは話していたんです。先生が中部大学に来られるということで博士課程に行きました。博士に入ったら学校の常勤はできないから、小学校の先生の資格を取りました。すでに職場経験があるから、通信である程度の科目と実習に行けば免許をもらえるんです。免許を取る時に自動的に講師登録されるので、それで小学校の非常勤に行っていました。 ―なんで小学校の資格を取ろうと思ったんですか? 野中:教育学部の教員の公募資格が、小・中・高の免許を持ってる人になるんです。だからあればあるほどよいかなと。中学校の先生をやっていなかったら、多分小学校の免許は取れなかった。その時は嫌だったし、こんなの私の人生に絶対に役に立たないと思っていたけど、振り返ってみたら何が役に立つかわからないなと思います。 ―中部大学ではいよいよエジプトについて調べることになるわけですね。 野中:それまで音楽学でいろいろ研究してきたから、音楽方面の分析はできるけど、エジプト学のバックグラウンドが必要なわけです。エジプト学と音楽学が混ざり合ったところに私の研究があるから。6年間は音楽学だったから、私にエジプト学の基礎がなかったんです。 ―でも県芸に入る時は逆でしたよね?音楽史の基礎がほぼなくて、エジプトの知識の方があった。 野中:今思えば、他の人よりはあったという程度です。私の知識が博士を取るまでのエジプト学になっていないことに先生はすぐ気づかれて「私の代わりにサテライトカレッジの講師をしなさい」と言われました。人に教えるのが一番勉強になるからとおっしゃって。それで博士課程に入ってすぐにエジプト講座をやることになりました。

マイクの握り方が完全に歌のそれですね
研究で一番大変だったのは遺物資料を見ること。学部の時は「アラブの春」でエジプトに行けなかったんですが、それがずっと続いていてすぐ行けるような状態ではなかったんです。でもエジプトのものは他国にあるものも多いんですよ。中部大学からいただける研究費を片っ端からいただいて、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、アメリカに行ったりしました。そこで当時ハンガリーに留学していた、京芸院時代の同期の中嶋弥生さん(*)が活躍してくれました。ヨーロッパに行く時には来てくれて、私の英語が拙かったので、弥生ちゃんからキュレーターに聞いてもらったりしました。エジプトに行けたのはコロナが流行する直前のことでしたが、それまでにほとんどのエジプト博物館に行った気がします。
* 中嶋弥生さん:2013年京芸大学院修了。ハンガリー国立リスト音楽院修了。元ハンガリー市立zugloi管弦楽団第一ヴァイオリン奏者。

古代エジプト音楽の研究者が何でいないのかといったら、研究が本当に大変なんですよ。音楽学もエジプト学もやらないといけない。音楽はやっぱり出土遺物が重要なんですよ。歌詞だけあってもわからないじゃないですか。絵だけあっても、実際はどういうものなのかわからない。図像資料、文字資料、遺物資料、全部ないと研究が厳しい。出土遺物を全部見なきゃいけないけど、エジプトにあるものだけでは数が少ないから本国に行くだけでも多分だめだし。そんな月日がかかることはみんなやりたくないですよね。もっと研究しやすいテーマはたくさんありますから。 → 後編へ続く

カルナック神殿にて