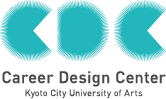インタビュー企画「表現のとなり」が始動します! アーティストの表現・発表の場を支える、コーディネーター、広報、キュレーターといった職業にフォーカスするインタビュー企画。 プロの方達はどのように社会と芸術を繋げる試みを行っているかをお伺いします。
アサヒグループ 大山崎山荘美術館
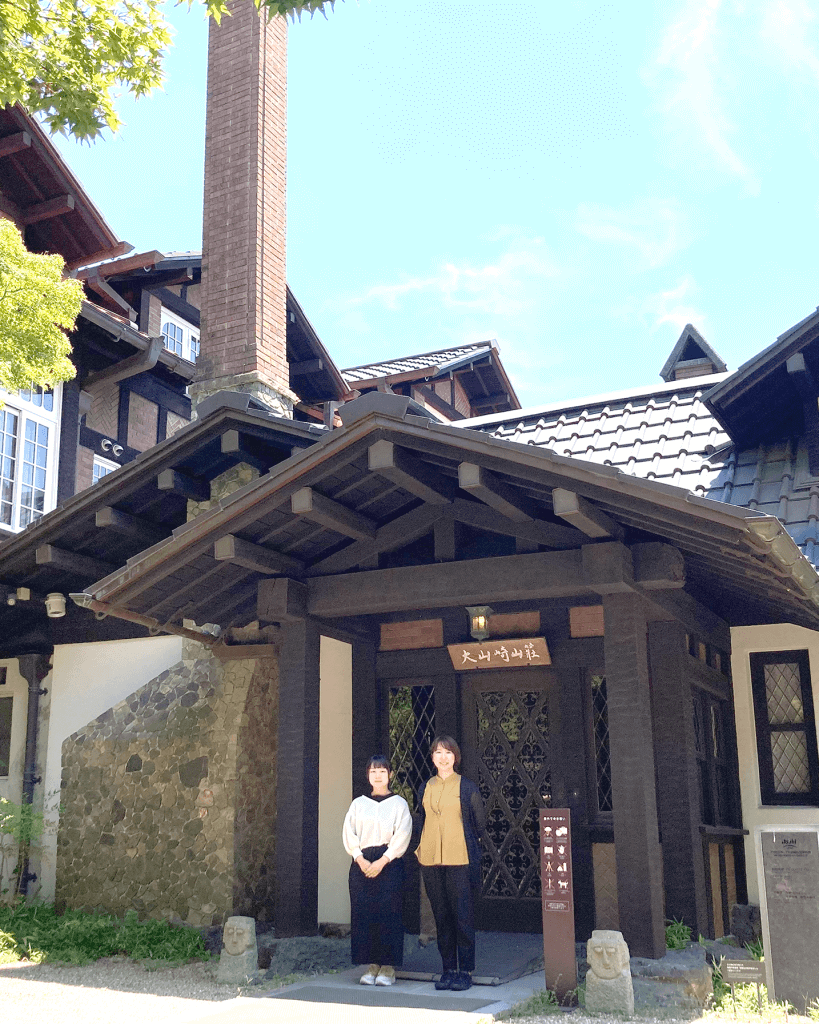
聞き手: 柳楽正人(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター音楽アドバイザー) neco(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター美術アドバイザー) (2025年7月実施)
◾️アサヒグループ大山崎山荘美術館について
neco:本日はよろしくお願いします。まずは、美術館の概要をお聞かせください。 池田:アサヒグループ大山崎山荘美術館は、名前の通りアサヒグループ財団が運営をしている美術館です。美術館では年に3回から4回、企画展を行っております。学芸員のほか、施設管理や運営広報、教育普及を担当する職員と、受付・監視・喫茶を担うスタッフで構成されています。 美術館の本館として利用している建物は築約100年の洋館で、大阪の実業家・加賀正太郎が造った建物です。最初は別荘として建てて、後に住居として使っていました。そうした「人が住んでいた空間」で作品をご覧いただけるというのが、ホワイトキューブではないこの美術館の特徴です。企画をする上で、学芸員たちも作家や作品と建築の関係性を意識して企画しています。例えば、昨年行った「アンドリュー・ワイエス展」は、アメリカのペンシルバニア州にあるオルソン・ハウスとよばれる屋敷に住んでいた姉妹と、作家の親密な関係から描き出された作品群が中心となった展示でした。お客様の感想などをお聞きしていると、本当にオルソン・ハウスに来たようだというお声や、作家と姉弟との関係を感じられるような展覧会だったというようなお言葉をいただきました。ホワイトキューブとは違った、建物の影響を受けながら作品を見ていただけるような展覧会が多いのではないかと思います。

neco:この建物について、詳しくお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。 池田:加賀は20代の頃にヨーロッパを遊学しており、その際に見聞きしたものがこの建物にふんだんに投影されています。加賀自身がデザインや監修を行っていて、ヨーロッパで得た知識や影響を受けた部分が見て取れるのですが、よく見ていくと和風な部分があったり、中国の骨董趣味も持っておりましたので、東洋風な装飾があったり、加賀の理想が詰まった建物なのです。 今から110年ほど前、1912年にこの建物を着工し、最初の5年で平屋建ての建物が作られました。今の美術館のエントランスの部分が、第一期の工事の部分が残っているところです。それをまた増改築しまして、鉄筋構造で地下1階、地上3階建ての、今のような形になったのが1932年です。実に20年ほどかけて改装や改築を繰り返してこのような形になりました。 加賀の没後、加賀家の手から離れて企業の保養所になったり、会員制のレストランになったりした時代もあり、その間に建物は老朽化していったようです。平成のバブルの時代になって、取り壊してマンションにする計画が持ち上がり、その際に、大山崎町に住まれている方や識者の方から反対運動が起きました。その反対運動が、当時の京都府知事の荒巻禎一知事の耳に届きまして、荒巻知事からアサヒビールの当時の社長・樋口廣太郎が相談を受けました。そのご縁でアサヒビールと大山崎町と京都府が協力して、美術館という形でこの場所を守っていくことになりました。ですので、美術館の建物はアサヒグループの管理になっていますが、お庭や他の建物などは京都府や大山崎町が管理しているところもあり、官民共同で守っていく場所になっています。 neco:コレクションについてもお伺いさせてください。 池田:コレクションの主軸のひとつは、西洋近代絵画の作品です。美術館としてオープンする際に新設された、安藤忠雄氏設計の「地中の宝石箱」と名付けられた建物では、常にモネの《睡蓮》を展示しています。アサヒグループとしては8点モネの作品を所蔵しておりまして、その中で5点は《睡蓮》の作品です。それを入れ替えながら、いつ来てもモネの《睡蓮》を見ていただけるようにしています。 また、朝日麦酒株式会社(現アサヒグループホールディングス株式会社)初代社長の山本爲三郎は、民藝運動を篤く支援しており、河井寛次郎の活動の初期から作品を購入していました。また、1928年に上野で開かれた大礼記念国産振興東京博覧会でのパビリオンとして、柳宗悦らが「民藝館」を出品したのですが、万博の終了後に、山本爲三郎がその民藝館を建物ごと買い上げて大阪に移築をしました。大阪の三国にあった山本爲三郎の自宅に移築をしたので「三國荘(みくにそう)」とよばれるようになりました。その山本爲三郎が集めた民藝運動ゆかりのコレクションを、美術館を開館する際に山本家からご寄贈いただき、西洋近代絵画の作品とともにコレクションの主軸となっています。

neco:建物を活かして展示会構成をされている美術館ということですが、メインの客層はどういった方なのでしょうか。 池田:一概に述べるのは難しいですが、美術ファンの方が来てくださる他に、文化財の建物に魅力があるということで、観光で来てくださる方も多いです。春になると庭園には桜が咲き、喫茶室のテラスからは背割堤という桜の名所も眺められます。秋になるとテラスからとても奇麗な紅葉がご覧いただけます。そういった景色や庭園、建物を見に来られる方がおられます。年齢層としては幅広い年代にお越しいただいておりますが、ミドル世代の、40~50代くらいから上の方が多くおられます。観光で初めて来たという方も多くおられますので、割合としては初めての方の方が多いかなという印象です。展覧会がお好きな方はリピーターで来てくださいますし、他の季節の景色も見てみたいということでリピートしてくださる方も多いですね。
◾️広報戦略について
neco:企画の立案から実際に展覧会がオープンするまでは、どういった流れになっているのでしょうか。 池田:展覧会は長いときは3~5年前から学芸員が企画、準備をすることがあります。広報チームが関わり出すのは大体半年~1年前くらいです。広報も含め、教育普及もどういうイベントをしていくかというところを一緒に考えていきます。広報に関してもイベントに関しても、少なくとも3年先ぐらいまでの予定は共有されますので、企画担当の学芸員と相談し、すすめていきます。 チラシやポスターなどの展覧会印刷物は、多くの場合、デザイナーさんとのやりとりや監修もトータルで学芸員が行っています。そのため、展覧会のイメージとチラシのビジュアルイメージの乖離が少なく、親和性が高いものになっているのではないかと思います。

柳楽:チラシを拝見していると、いつも好奇心をくすぐられるような文章やデザインになっていて、見ただけで「面白そう!」と思っていましたが、学芸員さんが監修されているということで納得しました。それでは広報チームは、チラシが出来た段階で動き出すわけですね。 池田:そうですね。プレスリリースを作ったりするのは我々の仕事なので、ビジュアルのイメージが出来るのと並行して、プレスリリースを作っていくところがスタートになります。 neco:企画展では、どういった方に届けることを考えながら広報戦略や計画を立てているのでしょうか。 池田:前回の企画展のアンケートも含めた、全体の総括が基本になってきますが、広報の主軸はやはりポスターとチラシ、それからSNSやウェブサイトです。もちろん企画によってターゲットが変わるので、広報としては展覧会ごとにどういったところにアプローチするがいいのか、どういった媒体にヒットするのかを研究して動いていきます。 neco:広報媒体で一番手応えがあるものは何でしょうか。 池田:なかなか難しいのですが、年齢層が高くなると紙物が強いですね。年齢層が高い方に向けて発信する場合は、新聞媒体やテレビ、ラジオなどで、40代から下に向けての場合はSNSが強いというのは如実に表れています。あとは、探り探りではありますが、例えば子ども向けの場合ですと、学校や教育関係の施設といかに連携していくかも大事です。子どもたち一人一人に手渡しをしてもらえるチラシがあるかないかというのは、そこからご家族に繋がるところでもあるので、大きいです。展覧会ごとにどういったところにアプローチしていくのがいいのかは、広報のチームと学芸員が協力して考えているような状況です。 柳楽:反応率などもチェックされているのですか? 池田:来館者アンケートが全てのような形にはなりますが、パーセンテージは常に把握している状況です。 柳楽:展覧会ごとに、メインのターゲットを変えておられるんでしょうか。 池田:そこまで読みたいところではあります。こういう展覧会だったらこの趣向の人、この年齢層、というのは回数を重ねてやっと見えてきたところでもあるので、今後はそういったところも活かしていきたいですね。2021年末から2022年にかけて開催した「みうらじゅん展」の時に特に感じたのですけれども、みうらじゅんのファンの方は40代より上が多いので、ラジオの反響が結構大きいと感じました。やはりターゲットの世代によって媒体を変えるのはすごく大事だなと思います。2025年冬に開催した「松本竣介展」は、その前の秋の企画展「アンドリュー・ワイエス展」の時と主になる年齢層が違っていて、チラシの効果が高かったです。ターゲットの年齢層に合わせた媒体をいかに選んでいくか、逆に弱いところをいかにフォローしていくかも含めて考える必要があります。年齢層が高い方に好まれそうな展覧会を、若い層にどうアプローチするかも考えていかなければいけないなとも思います。 柳楽:プレスリリースについては、何か工夫されたりしていますか? 池田:プレスリリースは、記者の方がそれを見て記事にしてくださることが多いので、どこに何の情報が載っているかがわかりやすくて、記事にしていただきやすい形態でお届けしたいなと思っています。デザインを変えてしまうと、どこから来たのかわからないところもあるので、ずっと使っているひな形はきちんと守りながら、情報が見やすいようにと意識しながら作っています。また、メディアの方には読者プレゼントという形で招待券をご提供させていただき、画像も無償で提供するので、掲載した完成物を送っていただくようにお願いをしています。そうすると、ある程度プレスリリースの反響は追えるので、それをひとつの成果物として記録をつけていっています。 neco:展覧会にあわせて、ギャラリートークなどのイベントもされていますよね。そういったスポット的なイベントの広報と、展覧会の広報は違いますか? 池田:実はイベントは集客人数に限りがあるので、そこまで広報をしていない場合もあります。先着順だと1時間で埋まってしまうこともあるので。参加していただける人数や規模によっても告知の頻度や方法を変えています。ただし終わった後の報告は広報にも繋がることなので、何をやったのかはSNSなどに必ず出しています。 neco:報告は大事ですよね。やりましたということをちゃんとオープンにする。 柳楽:案外やらない人が多いんですよね。自分は報告を出すときは、「来なかったことを後悔させよう」というぐらいの気持ちでやっています(笑) 池田:本当にそうですよね。こんなことやっているというのをまず知っていただいて、今度行ってみたいなと思ってくださったら、新たな来館者になっていただけるかもしれませんので。

◾️SNSの広報について
neco:美術ファンの方は美術館や規模の大きなコマーシャルギャラリーに行く方が多いかと思いますが、そういったところはスペースの問題などで、個人の作家のDMはなかなか置いていただけません。情報をどうやって発信していくかは、今はやはりSNSが大きく頼りになっている状況だと思います。 池田:SNSは表示される文脈の人たちが決まってきてしまうので、意外と狭い世界の中で収まっていて、なかなか難しいなとは思います。当館では私が着任させていただいた2019年から、InstagramとFacebookを始めました。当時、Instagramは若い人がやっていたので、上の年齢層をカバーしようということでFacebookも始めたのですが、最近ではInstagramも年齢層が高くなっている印象です。Instagramはストーリーズをもっと上手く使っていけたらなとは思っています。当館人気の定番コンテンツには、展覧会や作品紹介のほかにも「きょうの庭園情報」があります。庭園の風景は四季に合わせて移り変わりがあるので、それを投稿していくとお客様から反応があります。あとは喫茶室を中心としまた、食べ物関係も人気です。 neco:喫茶室では、展覧会ごとに毎回コラボメニューを出されていますよね。 池田:それも学芸員が中心となってやっています。作品にちなんだテーマのケーキなどは、リーガロイヤルホテル京都のパティシエさんとやり取りをして作っています。ありがたいことにお客様に喜んでいただけていますし、喫茶室を取り上げたいと言ってくださるメディアの方も多くいらっしゃいます。

neco:SNSは全て広報チームの方が動かすんでしょうか? 池田:SNSは、館発信のものと、外部の業者に頼んで有料広告として出してもらうものがあります。広告は、「美術が好きな40代女性」など、ある程度ターゲットが絞れます。有料広告を出すようになってまだ日が経っていないので、検証段階ではありますが、展覧会によってターゲットを変えていけるので、有料広告は効果的だなと思います。企画展ごとに、どれくらいインプレッションがあったのか、どれくらいの年齢層の人がアクセスしてくれたのかというのが数字で表れてくるので、それを見て次はどうするのか検証していくという形です。 柳楽:有料広告はどのくらいの期間出されていますか?長いほうがいいんでしょうか。 池田:展覧会の傾向や予算にもよりますが、どういう時期にどういうものを流すかというタイミングもあります。弊館ですと、展覧会だけの広告を流すよりも、紅葉の写真と一緒に載せるとか、池に咲くスイレンの写真とモネの《睡蓮》が展示されている写真を一緒に載せるとか、多分効果的な画像の組み合わせというのがあって、良いタイミングでお客様に情報が届くように、と考えています。弊館のさまざまな魅力を持ったコンテンツを組み合わせることで、もともと美術はそんなに興味がない方にも、美術館に行ってみようかなと思ってもらえる、だれかの「最初の美術館」になれるのでは、という可能性を感じています。

◾️教育普及活動について
neco:多くの方に来てもらうには、既存の方だけでなくて新しい客層に情報を届ける工夫をすることになると思います。新規客層の開拓のために何か試みはされていますか? 池田:これは私の担当になるのですが、そこが教育普及なんじゃないかなと思っています。昔、私が作家活動をしていた時に、教育普及を志すきっかけになった言葉がありました。初めてワークショップをやることになったとき、勉強のため、五感を使った教育を主にされている保育園に話を聞きに行ったのですが、そこで園長先生に言われた「文化の底上げをするなら、小学校や幼稚園といった全員が同じように教育を受けられるところにアプローチしないと、間口は広がらないわよ」という言葉がずっと残っています。「美術館だけでやっていたって好きな人しか来ないし、親が連れてきてくれる人しか来ないから、そこからは間口は広がらない。文化を底上げしていくには、美術、芸術をどうやって義務教育の中に入れていくのかが大事なのよ」という話をしていただきました。私にはその視点がなかったので、すごく衝撃を受けました。 美術を好きな方や美術に興味を持っている方じゃなくても、美術館に行って作品を見ようと思える環境や状況を作りたいと思った時に、最初にアプローチできるのは小学校であり、幼稚園であり、また生涯学習といった意味では、おじいちゃんやおばあちゃんになっても見に来られる状況を作ることなんじゃないかなと思っています。今は大山崎町の小学校で集中授業を行うなど、少しずつ活動しています。昨年から始めたミュージアムスタートプログラム「HOP・STEP・MUSEUM!」では、小学校3、4、5年生を対象に年1回、楽しみながら美術に興味を持ってもらうための授業を実施しています。3年生で当館の所蔵作品を知ってもらい、4年生で建物の歴史を知ってもらい、5年生でモネについて、作家の表現について話をさせていただいて、10歳前後の成長期に美術館として関わらせていただいています。

neco:企画展に関連した内容の教育普及もされていたりするんでしょうか? 池田:企画展では基本的に、講演会やギャラリートークなど、企画展の内容を深く知るためのイベントが主となります。学校と一緒にやっていこうと思うと、年度単位で考えなければいけないので、企画展と連動させた学校でのイベントというのは、なかなかできていない状況です。 neco:基本は美術館のコレクションと建物でプログラムを構成しているんですね。 池田:長期的な視点のプログラムはそうですね。特に子どもたちにとって、美術館のコレクションはすごく意味があるものだと思っています。というのも、中学生のときに見た作品と大学生のときに見た作品、また50代になって見た作品とでは、感じ方が変わるじゃないですか。企画展の作品は、展示が終わったらなかなか次に見る機会はありません。ですが、弊館であればモネの作品は、いつ来ていただいても見てもらえます。来年アサヒグループ大山崎山荘美術館開館30周年になりますが、30年前に見たモネと今見るモネとでは感じ方も見え方も変わってくると思うのです。そういった意味では、小学校でコレクションの話をしたり、コレクションに親しんでいただいたりするのは、すごく重要じゃないかなという思いでやっています。 neco:美術館には収蔵品があって、それを常設展で見られるというのを、知らない人が意外とたくさんいます。企画展をやっているものだと思っている方がたくさんいますよね。それぞれの美術館のカラーが見えるのはやっぱり収蔵品ですし、コレクション展なので、それを子供のうちから見られる機会がたくさんあるというのは、すごく良いことだと思います。 池田:本当にいいことだと思います。私は岡山で生まれて育っていまして、岡山には倉敷に大原美術館があります。大原美術館は、幼稚園の時から通えたり、小学校になったらこういう関わり方、高校生になったらこういう関わり方、大人になってもボランティアスタッフで関われたりするといったように、年代に合わせて作品や美術館と関わることができる機会がすごく充実していました。それを見てきたので、コレクションを通じて、鑑賞者の人生にいかにかかわるかは、美術館が考えるべき視点であり、探求すべき可能性を感じています。私は中学の時、美術の先生に美術館に行きなさいとすごく言われました。作品をみて、自分だったらどうするかをしっかり見てきなさいとよく言われていました。 neco:私も過去に、そうやって言ってくださった先生がいました。見に行かないと自分が作ったものが良いかわからないから、行けるものは全部行ってこい、と言われました。 池田:そう思うと、中学や高校の先生に来ていただいくというのも大事なのかもしれないですね。 柳楽:お話を伺っていると、子どもたちを育成するのも大切ですが、先生を育成するという方向もあるもかもしれないですね。トータルで広げられる子どもの人数は増えるので。 neco:あとは、美術だと塾の先生、音楽だとレッスンに行っている先生など、影響力が大きい人たちですよね。 池田:確かに大事ですよね。先生は影響力ありますから。いいアイディアをいただきました。 柳楽:教育普及の活動は、池田さんが来られてから始まったことなんですか? 池田:過去、大山崎町の小学校6年生対象の出張授業や、休館日の地元小学校の見学受け入などは行っていましたが、コロナの時期を挟んで途絶えてしまいました。コロナがあけ、地元教育委員会や学校にご協力をいただき、新たに「HOP・STEP・MUSEUM!」の企画を立ち上げさせていただきました。実施は2024年から、やっと動き出すことができました。 また、近隣の名建築「聴竹居」とのコラボレーションツアーは2010年頃から続いています。近年は大山崎山荘単体のツアーのバリエーションも増やし、いろいろな視点で美術館を楽しんでいただける取り組みを増やしています。 neco:学校へは学芸員の方がいかれるのですか? 池田:教育普及担当者が行きます。子ども達には美術の道に進まなくても、観ることは楽しい、ということをお伝えしたいですし、気軽に美術館に足を運んでいただけるように働きかけたいです。美術館は普遍性も感じられるし多様性も感じられる。自分の変化を見直せる場でもあるので、何回でも来ていただきたいし、それを広めていきたいというのはありますね。 柳楽:個人的に、美術館に何回も足を運ぶことの意味を教えていただける方が今までにいなくて、一回見たらそれでいいやと思ってしまっていました。今お話しを伺って、そうなんだ!とずっと思っていました。 池田:何回でもいらしてください!

◾️やってみたいこと
柳楽:広報に人手やお金をどれだけでも使っていいと言われたら、やってみたいことはありますか?という夢の話をお伺いしたいのですが、竹中さんはまだ来られて間もないということなので、今までの経験でもいいですけど、制約がなかったらこういうことがしたかったなということはありますか? 竹中:今までは広報活動をするとなるとまずはお金をかけない方法から始めてということで、アポを取って置いてもらって、またアポを取って置いてもらってというのが中心でした。ですから大々的な有料広告には憧れがありました。今後は特にSNS方面の広告を積極的にできたらいいなと思います。投稿頻度を増やしたいです。 柳楽:今はどのくらいの頻度で投稿されているんですか? 池田:自分たちでは2週間に1回は必ず、できれば1週間に1回投稿したいと思って運用しています。欲を言えばもっとしたいです。 neco:SNSはやっぱり数になりますよね。出す数でリーチが全然違いますから。池田さんは人もお金も自由に使えるとしたら、やってみたいことはありますか? 池田:電車広告を出したいです!電車に乗っている間は吊ってあるものが目に入るので、ゆっくりと見ていただけて良いなと思います。これまで駅の改札口のデジタルサイネージに映像を出したりもしましたが、足を止めて見ていただくことはなかなかに難しいと感じます。 neco:教育普及の面でも、制限がないと言われたらやってみたいことはありますか? 池田:もしそう言われたら、いろいろな学校に行きたいです。今はマンパワーも足りていないので大山崎町の小学校しか行けていないのですが、中学生や高校生・大学生も含めて地域や年代を広げて、教育機関と連携しながらそれぞれに適したプログラムを考えていきたいです。あとは生涯学習という意味で、年齢の高い層に向けても何かしていきたいというのはあります。ただ、弊館はとても小さな美術館ですので、どうしても空間的にたくさんの人をお呼びするのが難しいという状況もあります。それこそお金があったら、ワークショップ棟を建てて専用のレクチャールームを作ったりしたいですね! 柳楽:夢は広がりますね。本日はありがとうございました!

◾️インタビュー後記
neco:興味深い話がたくさんありましたね。教育普及の話が根源的だなと思いました。単なる出前授業ではなく、未来の鑑賞者を育てるとか芸術に興味を持ってもらうという意識でされていると感じました。 柳楽:池田さんはずっと以前から構想を練っておられたんでしょうね。いざ実行するとなるととても大変なことだと思うので、教育普及の分野はすぐに取り入れられない部分でもありますね。 広報の部分では、企画ごとにターゲットを明確に意識して変えておられるという話が興味深かったです。例えばクラシックのコンサートだと、演奏者が同じなら宣伝の仕方もターゲットも大体同じだと思うんですよ。演奏する曲がベートーヴェンからシューマンになったからといって、基本的には大きくターゲットが変わったりはしていないと思うんです。 neco:でも、もしかしたら変えられるかもしれないですよね。こういうものに興味がある人ならこのコンサートに来てくれるかもしれないとか。何かの映画と関連づけてみるとか。そう考えると、まだまだ開拓の余地はあるかもしれないですね。美術でも、その企画がどういうところと接続できるかということを美術館や施設の方で考えているというのは、あまりないかもしれません。 柳楽:この企画はこういう層がターゲットかもしれない、という考えにそもそも及んでいない人も多いと思うので、そこをずっと考え続けておられる人とは差が広がり続けるなと感じました。 neco:それと、イベントごとに終わった報告を出すというのは、やっぱり大事ですよね。来られなかった人をいかに次に繋げるか。コンサートが終わった後の演奏者の気持ちとか、展示をどういう風に構成したのかという話は、きっと興味があると思います。おろそかになりがちですけど。 柳楽:池田さんのお話はとてもよかったですね。定期的に勉強に行きたいぐらいです(笑) neco:これからいろいろな施設の方にお話をお伺いできたら、さらに広がりそうですね。