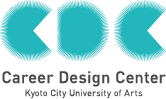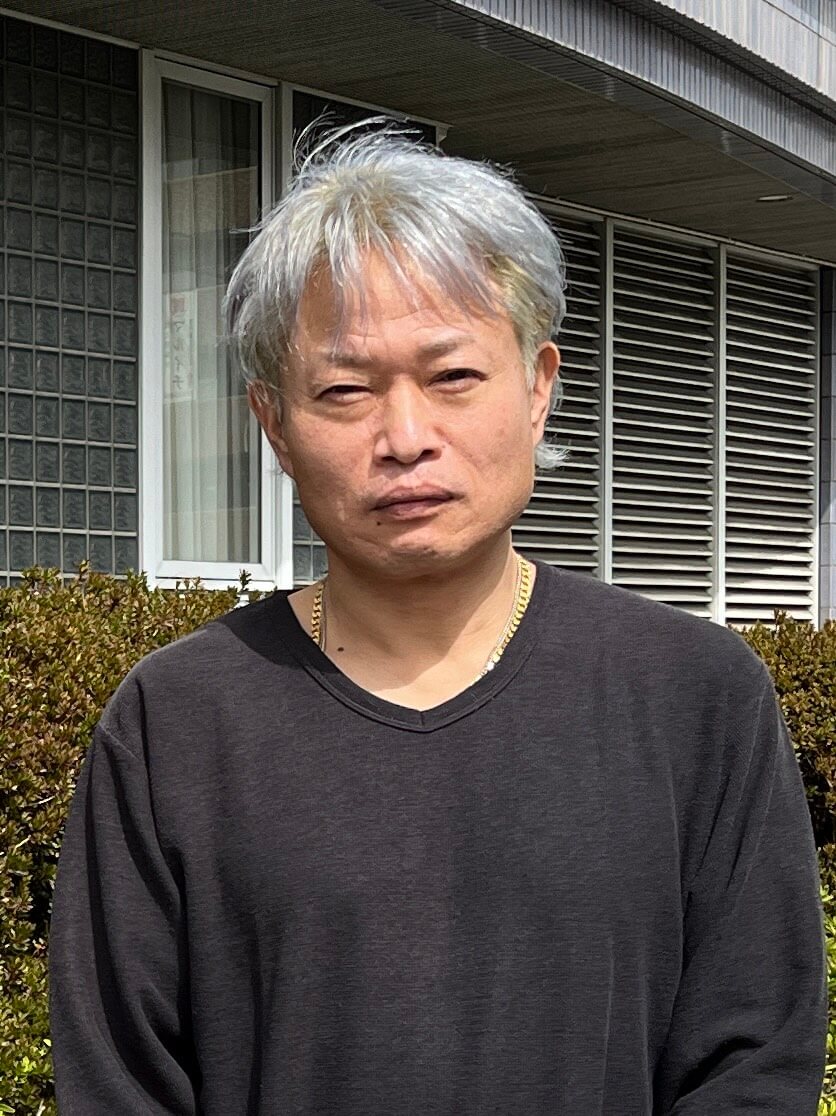
黒飛雅之(ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団チーフマネージャー) 京都市生まれ。京都市立堀川高校音楽科(現京都堀川音楽高校)卒業。少し社会勉強期間を経て、京都市立芸術大学音楽学部入学。卒業後、フリーのホルン奏者や社会勉強期間を経て、2003年より京都フィルハーモニー室内合奏団ステージマネージャー、営業、事務局長、理事等を歴任。2019年同団退職。2020年よりザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団チーフマネージャー。書道準特級。暗算検定2級、珠算検定1級。普通自動車第一種運転免許取得。危険物取扱者免状乙種4類取得。テールゲートリフター操作特別教育修了。
インタビュー:柳楽正人(京都市立芸術大学キャリアデザインセンター音楽アドバイザー)
■演奏活動を辞めて京フィルの事務局に ―黒飛さんはかつて京フィル(京都フィルハーモニー室内合奏団)の事務局長をされていて、今はオペ管(ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団。大阪音楽大学の施設「ザ・カレッジ・オペラハウス」専属のプロオーケストラ)の事務局におられるというのは知っているんですが、どちらも気がついたらいつの間にかそうなっていたんですよ。まずは大学を卒業した時期からの道のりを伺えたらと思います。 黒飛:大学を卒業してから、バイトもしながらでしたけどフリーランスのホルン奏者として活動していました。それなりに仕事はあったんです。だけどある時、ここで辞めようって思ってパンって辞めたんです。それが30歳ぐらいの時ですね。ちょっともう無理だなって思ったんです。演奏技術以上に、舞台人に向いてないなって。そこからは来た仕事も受けずにお断りしました。 ―次の仕事を決めてたわけじゃなくて、とりあえず辞めたんですね。 黒飛:そうなんですよ。何でそう思ったのか、その時にはあんまりわからなかったんですけど、後々になって、あ、これだなと思ったことがありました。京フィルでステマネ(ステージマネージャー。舞台の進行を管理し、事前事後の雑務を統率する人)をやっていたときに、楽団員がソリストで協奏曲をやるというプログラムがあったんです。僕は舞台袖にいたんですけど、ソリストが本番を終えて袖に帰ってきたときに、開口一番「楽しかった!」って言ったんです。僕は絶対にこんなこと言えない。あそこで失敗したとか考えてしまってそういう心情にはなれない。そういうのができる人じゃないと舞台人になったらダメなんだなというのが、当時の思いと繋がったんです。 そこからは全然違うことをやろう、バイトじゃなくてちゃんと勤めないとと思って、新聞広告の求人を見たり、資格のチラシを見たりとかしていました。でも僕は堀音(京都市立堀川音楽高等学校)からこの業界にいたから、それまでの人生の半分ぐらいずっとクラシックの世界にしかいなかったんです。だから外に目を向けよう思っても何にも興味が持てない。そのまま結局2〜3年ぐらい働かなかったんです。バイトもしないで貯金を食いつぶす生活。そんな時、僕がぶらぶらしてるのを知っていた京フィルの越川雅之さん(*)からたまたま呼び出しがあって、京フィルの営業職が1人抜けるから受けてみない?って言われたんです。
* 越川雅之さん:1997年京芸学部卒業。2001年より京フィル打楽器奏者。
―たまたまじゃなくて、まさにその話で呼び出されたんじゃないですか(笑)。越川さんは京芸の先輩だったんですよね。 黒飛:それで面接に行ったんですけど、その時は受からなかったんですよ。その後、今度は京フィルの運転手の面接を受けてみない?って言われたんです。京フィルは練習場がないから毎回どこかに行かないといけなくて、楽器とかをトラックで運ばないといけなかったので専属の運転手がいたんです。その人が辞めることになったんですよ。それで面接に行って、そこで採用されました。運転手ではありますけど、結局は簡単なステマネみたいなところまでやるので、運転手兼ステマネみたいな感じでした。 その頃の京フィルはまだ色んな活動はしていなくて、やることは大体同じだったんです。15人ぐらいの編成で学校を回ったりとか、ステージの組み方がある程度決まっていたので、楽員さんも一緒にやったりしていました。だけど僕が入ってしばらくしてから、大きい編成だったり色んな活動をし始めました。そうすると楽員さんも何でもかんでもはできなくなってきたので、ちゃんとしたステマネが必要になって、それならステマネをやってみない?って言われたんです。 ―それまでの京フィルは、ステマネというポジションはなかったんですか? 黒飛:なかったです。何となくみんなでやりあっていた感じです。それまでは運転がメインでちょっとステマネだったのが、運転もしながらステマネの仕事がドーンと追加されたみたいな感じになりました。 ―ステマネになっても運転の仕事がなくなるわけじゃないんですね。 黒飛:最初はそうでした。それだけじゃなくて、例えば学校公演で事務方が現場に来られない時は校長先生とご挨拶したり、担当の先生と打ち合わせをしたり、そんなのもやらないといけない時もあったりして、何でもしないといけない。入って5年ぐらいがそんな感じでした。それから、事務局の体制がちょっと弱いというか、営業強化をしないといけないとなって、現場の業務を手放して僕が事務局に入ったんです。 そこからまた5~6年くらいして、事務局長という肩書きになりました。事務局長と言いながらも営業にも行ったり、他の事務局員の手が回ってないところを手伝ったり、結局は何でも屋でしたけど。その頃はライブラリアン(楽譜の管理全般をする人)がいなかったんです。ずっと楽員さんが全部やっていて、それもある程度パターンが決まっていたからできてたんですけど、時々全然違うものが入ってきたりするとやっぱり無理になるので、その時は僕がライブラリアンもどきのこともやったりとか。色んなことをやっていたのが7年くらいです。そこまでで入ってから12年くらいですかね。結局15年ぐらいいたんですけど、最後の1年は大変すぎて、どうにもできなくなって辞めました。よくも悪くも色んな経験を浅くしていた感じですね。
■京フィルからオペ管のチーフマネージャーに ―浅くと言ってますけど、結構濃くて深めだったんじゃないですか? 黒飛:そんなことはないです。他の楽団に行っても多分通用しなかったと思いますから。京フィルを辞めてからは、いつまでとは決めずに仕事をしない時期がまた始まりました。そうしたら、オペ管で人が足りなくて探してたんです。京芸の後輩がオペ管のステマネになっていて、僕が京フィルを辞めたのを知っていたから、どうですかって声をかけてくれました。それで面接に行って採用されました。京フィルを辞めてからオペ管に入るまでの期間は10ヶ月くらいです。 ―オペ管はプロのオーケストラでもあるけれど、大阪音楽大学という大学の組織でもあるから、ちょっと立ち位置が特殊ですよね。 黒飛:最初に入った時は立ち回りというか、どこへ何を言ったらいいのか全くわからなかったですね。たまに日本オーケストラ連盟(*)の会合に出るんですけど、話の中心はやっぱり正会員のオケの話なんですよ。大きいオケが色々と画策されるのはいいことなんですけど、うちらはまた別という感じはします。
* 日本オーケストラ連盟:日本に所在するプロのオーケストラが加盟している公益社団法人。関西にある正会員オケは京都市交響楽団、大阪交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、日本センチュリー交響楽団、兵庫芸術文化センター管弦楽団の6つ。京都フィルハーモニー室内合奏団や、ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団は準会員。
―オペ管は最初からチーフマネージャーというポジションだったんですか? 黒飛:最初からチーフマネージャーで入りました。1年間だけステマネ兼任です。依頼公演の窓口とかは僕がいろいろやったりしています。ステマネもライブラリアンも総務も一応いるんですけど、チーフマネージャーと言いつつ何でもしないといけないんです。文化庁の巡回公演とかにもついて回りますし。現場には行かないといけないので、結局ステマネみたいなこともやらざるを得ない。 ―その辺りは京フィルの時と似たような動き方ですね。ちゃんとこれまでの経験が活かせる仕事に就いている。 黒飛:たまたまですけどね。でも割と人に導いてもらったところはありますね。学生の時、演奏旅行(*)ってあったじゃないですか。京フィルに引っ張ってくれた越川さん、オペ管に引っ張ってくれた後輩の2人に関しては、こじつけかもしれないですけど、演奏旅行で一緒に動いてた人たちなんです。僕は後輩がやってた年にも借り出されたんですよ。そんな繋がりがあったというのは、ひとつの縁かなとは思います。単に同級生とか先輩、後輩というだけじゃなくて、一緒にやってきた仲間みたいな。
* 演奏旅行:夏休みに音楽学部の有志でオーケストラを編成して、各地の学校に出向いて公演を行う。
―音楽学部は1学年60人という規模感もあるかもしれないですね。学生数が多い大学と比較すると、自分の専攻だけではない繋がりもあるだろうし。 黒飛:同級生全員と喋れたかと言うとそうでもないけど、割と近しく喋る人もいました。まあ、その人たちと未だに仲がいいのかと言われると、全く疎遠ではあるんですけど。 ―今は疎遠でも、またどこかで繋がるタイミングもあるんだと思いますよ。全く知らない人から声をかけられるのとは全然違いますからね。

■大工の息子がたまたま音楽高校に進学 ―黒飛さんは高校は堀音に行かれてたということですが、その時は将来は音大に行ってオケに入りたいと思っていたんですか? 黒飛:最初に楽器を始めたのが小学校なんですけど、小学校にトランペットクラブというのができたんです。うちは父親が大工だったし音楽とは全然縁のない家だったんですけど、ちょっと興味が湧いてやってみようと思ったんです。トランペットクラブにはトランペットが3本とトロンボーンがあったんですが、当時僕は体が大きかったんで、否応なくトロンボーンになりました。そこでトロンボーンをちょっとだけやりました。 それから音楽の授業で音楽鑑賞でホルンを聴いたんです。確かモーツァルトのホルン協奏曲の第1番。僕はあんまりあれこれ買ってくれと言う子供ではなかったんですけど、ホルンが欲しいってお願いして無理言って買ってもらったんです。今考えたら滅茶苦茶だなと思うんですけど。でも、買ってもらったのはいいけど、全然吹けなかった。トロンボーンとかトランペットは学校にある楽器を吹いていて、トランペットの指使いもわかるんですけど、同じ指使いをしてもトランペットと同じ音が出ない。当たり前ですよね。 ―トランペットとホルンは管の長さが違うから、同じ指使いでも違う音が出ますよね。 黒飛:なんでだろう、わからないなぁって悩んでたんですけど、小学校の同級生でトランペットを習いに行ってた奴がいたんです。同級生が京都市交響楽団のトランペット奏者に習っているのを知ってたから、ホルンを教えてくれる人がいないか先生に聞いてみてってお願いしたんです。そしたら先生が「俺が教えるよ」って言ってくださったんです。それで中学1年生からレッスンに行きだしました。漠然とただ吹けるようになるためなんですけど。 先生は堀音でも教えておられて、同級生は堀音を受けるためにレッスンに行ってたんです。それで中2か中3ぐらいの時に「お前も堀音を受けてみない?」って言われました。何か他に目標があるわけではなかったし、じゃあやってみようかなと思って、そこからピアノとかソルフェージュのレッスンもはじめました。先生の奥さんがピアノを教えておられて、娘さんは声楽だったのでソルフェージュを教えてもらって。1日に詰め込まれていて地獄のレッスンでした(笑)。そんな感じでやっていたら、受かってしまったんです。 ―先生に受けてみないかと言われたんだから、もともと見込みはあったんでしょうね。 黒飛:全部たまたまですよ。父親は小学2年生の時に亡くなったんですけど、それまでは自分は大工になるとしか思ってなかった。父親はどこかの工務店に所属してたので、店を継ぐとかそんなのではないです。ただ漠然と、やりたいなぁぐらいでした。でも亡くなってからは、別に何かになりたいというのはなかった。本当にたまたま堀音に入ったんです。
■本当にオーケストラに入りたいんだろうか?という疑問 ―堀音にはたまたま入ったとして、そこからはどうだったんですか?東京藝大を受けようとかそういう感じでした? 黒飛:そうです。2年間は東京藝大しか受けなかった。その頃はオーケストラに入りたいと思ってたんだと思います。だけど京芸に入ってぐらいですかね、あんまりそういうのが実感として湧かないようになってきました。憧れがなくなったわけではないんですけど、本当にこうなりたいのかなとか、こんな生活がしたいのかなとか思いだしたんです。これは偏見ですけど、面白くもない演奏会に引っ張り出されて演奏してるんじゃないかとか、仕事をこなしているだけなんじゃないかとか。 ―プロのオーケストラに対して、そういう疑いのイメージを持ってしまったんですね。 黒飛:学生の時の演奏旅行って、もちろん学生だからですけど、ひとつの演奏旅行を完成させることに色々と思い入れがあった。でも仕事になると、多分そんな思い入れはないんじゃないかって思ったんです。卒業してフリーのホルン奏者として活動するようになって、実際にやっぱりそう思ったし。それでちょっと萎えたところがあるかもしれません。本当は団員ひとりひとりはそうじゃないのかもしれないですけどね。 ―じゃあオーケストラには行かないとして、それ以外の活動で演奏を続ける考えはなかったですか? 黒飛:あんまりそういう未練はなかったですね。楽器が嫌いなわけじゃないですけど、ホルンももう辞めようと思いました。今は全く吹いてないですね。 ―演奏活動を辞めて仕事を探してた時、これだったらやれるかもという仕事は見つからなかったんですか? 黒飛:ちゃんとした仕事に就こうと思いながらも、手っ取り早く、思い入れもない時給1,500円の工場でモノを組み立てる仕事とかでもいいかなと思ったりもしました。だけど、いや、やっぱりちゃんと勤めなきゃだめだと。本当は大工とかも考えたんですけど、30歳から大工って多分無理なんです。僕の親父は組み木をがっつり作ったりしてた技術職だったから、そんな風には絶対なれないと思って。結局、就職の面接に行ったことは一度もないです。音大を出ているからこそという強みがパッと思いつかないんですよ。 ―一般社会の中での「音大卒の強みとは?」というのは永遠のテーマですね。 黒飛:やっぱりそう思うと、どこかで音楽をやりたかったのかもしれない。演奏活動を辞めてから、本当は早々に仕事を見つけて働かないといけなかったとは思うんですけど、なまじかバイト時代の蓄えがある程度あったから食い潰せた。もしそれがなかったら、スネをかじれる親でもなかったから、腹を据えて何が何でも探したと思いますけどね。そうなったら音楽関係とか言ってられない。言える余裕があったから、ずるずる長くなってしまったかもしれないです。 ―その時にぱっと仕事を見つけて就職していたら、今どういう人生だったんでしょうね。そこからステマネにはなってないでしょうし。 黒飛:いやでも、今は時代も変わってますけど、30歳過ぎてからどこかに新たに採用されたとしても、出世コースとかにはなかなかならないですよ。それまでの経験があった人ならまだしも、僕はほぼバイトしかやってないから。音楽と関わりがなくても、何かやっておいた方がいいと思いますね。演奏活動をしながらでもいいですけど。僕はバイトは色んなことはしていなくて、ほぼガソリンスタンド1本だったんですよ。バイト先の居心地がいいとか悪いとかもあるんでしょうけど、ひとつじゃなくて色んなことをやっておいた方がいいって、後になったら思いますね。
■京芸時代の演奏旅行で築いた人との関係 ―音楽を勉強していると、ある種特別で狭い環境の中で過ごしがちなので、世界を広げておくことは大事ですね。それにしてもガソリンスタンドの仕事がすごく性に合ってたんですね。 黒飛:合ってたんです。浪人時代から始めて、在学中も卒業してからもやってたんですよ。結局そのスタンドは潰れましたが、大学を出たらうちに来てほしいみたいな話もあったんです。断りましたけど。 ―その時はまだ演奏家としてやっていくつもりだったんですもんね。でもオーケストラに魅力を感じなくなった中で続けていくのは、辛い状況ではありますね。先が見えないというか。 黒飛:本当に食べていくためだけ、お金をもらうためだけ。せっかく声をかけてもらったから、その人も立てないといけないしとか考えたり。ただこなしていただけでした。大学を卒業してすぐの頃は、どこかのオケに入れたらなという気持ちが少しはあったかもしれないけど、でもやっていけばやっていくほど、プロオケに対する魅力が薄れていった。大学の演奏旅行でやっていた時のいいイメージがずっとあって、どこかでそれと対比してたかもしれないですね。ああいう風な思いで仕事はできないんだなと思って。 ―学生時代の演奏旅行はすごく重要なイベントだったんですね。 黒飛:僕の中では大きかったかもしれないですね。委員長もやったし。どこの学年もそうだったかもしれませんけど、委員の中ですったもんだあったりとかして「お前らもう来るな!」みたいなことになったり、それでも何とか出来上がって、みたいなね。いい思い出でもある。自分たちで立案もして思い入れも強かったんだと思います。 ―黒飛さんにとっては「たまたま」が続いてきた人生だったかもしれないけど、でもそれは演奏旅行などで作られた価値観で選択してきた道だっただろうし、学生時代に築いた信頼関係が、時を経て目に見える形でまた現れただけという言い方もできますよね。実は「たまたま」じゃなくて、ちゃんときっかけの種は自分で蒔いていた。 黒飛:今の仕事のことに関して、人の繋がりという部分での下地は、堀音よりも京芸の時の経験のほうが大きいかもしれないです。高校の時はそういう考えにもなっていなかったし、劣等感が満載だったので。僕は人付き合いがいい方だとは全然思わないですけど、どこかで誰かが引っ張ってくれていると感じます。
■音楽を裏で支える仕事 黒飛:演奏旅行って今もあるんですか? ―ありますよ。演奏旅行に行って京都に帰ってきた最終日に、桂坂小学校で公演をするのがセットになってるのかな? 黒飛:桂坂小学校の公演って、昔は堀音が行ってませんでした?桂坂小学校だったか忘れましたけど、堀音が桂坂の学校に演奏に行った時に、人が足らないからと言ってエキストラで参加して、それを最後にホルンを辞めたんです。割とキツいプログラムでした。あの曲をやりましたよ。指揮者の外山雄三さんの……。 ―外山雄三さん作曲の「管弦楽のためのラプソディー」ですか?確かに高校生には大変そうです(笑)。外山さんは一昨年(2023年)お亡くなりになりましたけど、海外でも認知されている邦人作品だから、これからも演奏し続けてほしいですね。邦人作品で言うと、武満徹さんの「ノヴェンバー・ステップス」なんかは、武満さんが亡くなって以降、オーケストラのコンサートでも録音でも聴く機会がほとんどなくなりましたよね。 黒飛:武満さんは小さめの編成の室内オーケストラ的な曲も書いていたので、京フィルにいた時に何回か武満徹シリーズみたいなのをやりました。指揮者の齊藤一郎さんが音楽監督の時代に邦人作曲家の作品をよくやっていたので。齊藤さんの時代には結構色んな経験をさせてもらって、僕自身ものすごく刺激を受けました。邦人作品を取り上げた定期演奏会で、佐川吉男音楽賞の奨励賞(*1)もいただきました。 ―そうした取り組みを評価していただけるのは嬉しいですね。大阪音大も邦人オペラの上演で賞を取られていますね(*2)。 黒飛:昨年はオペ管でも佐川吉男音楽賞をいただいたんです。モーツァルトの「劇場支配人」と、サリエリの「はじめに音楽、それから言葉」の2つのオペラをコンサート形式で上演した定期演奏会です。これは当時2人が同じ宮廷で同じ日に上演するために競作したオペラでした。 ―京フィルもオペ管も、黒飛さんが関わった時期に素晴らしい功績を残されているんですね。これはもう「たまたま」だけでは説明がつかないんじゃないですか?黒飛さんには「たまたま」という名前の、運を引き寄せる力があるということにしておきましょうよ(笑)。これからも音楽を陰で支える大黒柱として、益々のご活躍をお祈りしています。今日はありがとうございました!
*1 江村哲二さん、久保摩耶子さんらが東日本大震災の時に作曲された作品を演奏した第203回定期公演「三陸のうた・祈り」で、2016年度第15回佐川吉男音楽賞の奨励賞を受賞。 *2 1997年に黛敏郎「金閣寺」がABC国際音楽賞、大阪舞台芸術賞、三菱信託音楽賞を受賞。2003年と2005年に松村禎三「沈黙」が大阪文化祭賞グランプリ、音楽クリティック・クラブ賞、文化庁芸術祭大賞を受賞。
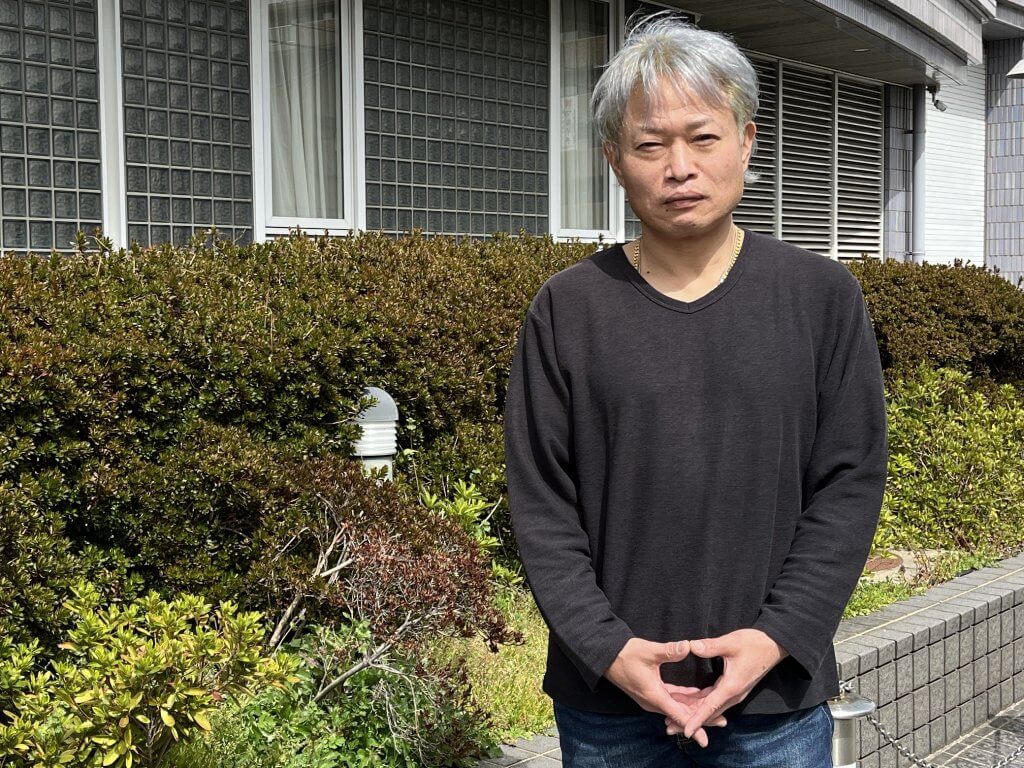
今回のインタビューでは、黒飛さん個人の道のりを中心に伺いましたが、コンサートを裏で支える立場としての心得もぜひお聞かせいただけないかと思い、インタビューが終わった後にあらためてメッセージをいただきました。ステージマネージャーの責任ややりがいが伝わる内容ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。
■ステージマネージャーは舞台における総責任者 コンサートは、出演者はもちろんのこと、接客対応スタッフ、会場の技術スタッフ、ステージマネージャーやライブラリアンなどの音楽スタッフ、企画制作、広報担当など、観客の目に見える部分だけでなく、その裏側にいる様々な役割の人たちが携わっています。ステージマネージャーは、ステージコンサートにおける「舞台上演に関する統括者」です。公演の準備や関係各所との調整からはじまり、公演に向けて出演者の気分を盛り上げる、本番の進行全体を司る、音響効果や奏者同士のコンタクトに相応しい舞台配置や転換を行う、公演中の不測の事態に備える、事が起これば速やかに適切に対処する、などなど。そして公演が終わった後も、諸々の処理があります。公演の主役はもちろん出演者であり、演奏技術そのものは奏者次第ですが、ステージマネージャーはその他の要素の全権を担う、文字通り「総責任者」なのです。 ステージマネージャーの判断ひとつで、公演の良し悪しに大きな影響を与えることがありますし、場合によっては、指揮者や演奏者、公演主催者よりも重い責任や権限を有します。時に、血走るような目つきで、張り詰めた空気を醸し出しながら神経を研ぎ澄ませているステージマネージャーに出くわす場面もありますが、経験のある身としては「むべなるかな」。その気持ちはよくわかります。 かつて、ある指揮者の方から「公演においては、ステージマネージャーは誰よりも偉い立場。心して従事するように」という助言をいただき、身が引き締まりました。ステージマネージャーをしていた頃は、その理想を追い求めても完全に務められるまでに至らなかったと思います。それでも公演が滞りなく終わり、いい上演ができて観客からもいい反応を得られた時は、何とも言い難い充実感を味わえました。(しかし浸り切る隙は許されず、すぐに次の公演の準備に追われるのです……)