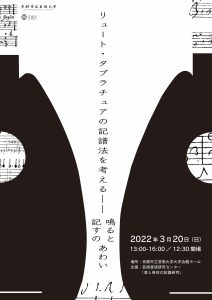「音と身体の記譜研究」プロジェクト企画
ワークショップ企画「ヴィオラ・ダ・ガンバ講習会」
「記憶装置としての楽器」
本ワークショップ(講習会)は、「記憶装置としての楽器」(高橋悠治, 2010)というコンセプトにもとづいて行うものです。
楽器は、それが使われていた時代の文化や社会、そしてその中での音楽の習慣を反映しています。たとえば楽器の音色や音質は、その楽器が演奏された空間と切り離すことはできません。弦の数や弓の持ち方は、それを操る身体(からだ)やそこからうまれる音楽と強く、深く結びついています。そして、そうした空間や身体からうみだされた音楽を記録し、新たに創造する術(すべ)としての記譜法、その時代の音をいまの時代に再創造・再想像するためのツールです。
今回のワークショップでは、スペインの作曲家、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者のディエゴ・オルティス(ca. 1510-ca. 1570)の残した数々の「レセルカーダ」のオリジナル譜を教材として用いながら、ヴィオラ・ダ・ガンバが鳴り響いた時代の音と身体の結びつきを想像してみようということで企画したものです。
「音と身体の記譜研究」プロジェクト・リーダー 竹内直
「ヴィオラ・ダ・ガンバ講習会」
講 師:頼田麗(ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者)
日 時:2024年8月20日(火)/21日(水)10:00-17:00
会 場:京都市立芸術大学 笠原記念アンサンブルホール
受講生:弦楽器を専門的に習っている高校生・大学生:最大12名まで/要予約
▶︎受講生申込用フォーム
一般参加者(聴講):定員50名/要予約
▶︎一般参加申込用フォーム
参加料:受講者・一般参加者ともに無料
企画・主催:京都市立芸術大学芸術資源研究センター「音と身体の記譜研究」プロジェクト
講師プロフィール
頼田麗(ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者)
相愛大学音楽学部卒業。ヴィオラ・ダ・ガンバを平尾雅子氏に師事。ルガーノ・コンセルバトーリオにてV. ギエルミ氏に師事。バーゼル・スコラ・カントールムにてP. パンドルフォ氏のもとで研鑚を積みディプロムを取得。2007年ドイツの第4回テレマンコンクールにて「ベーレンライター賞」受賞。2008年兵庫県知事グランプリ賞を受賞。「プリンチピ・ヴェネツィアーニ」「アンサンブル・ポエジア・アモローザ」メンバー。相愛大学音楽学部非常勤講師。
【企画アドヴァイザー・協力】
三島郁(音楽学/相愛大学教授、本学非常勤講師、芸術資源研究センター共同研究員)
【企画コーディネーター】
竹内直(芸術資源研究センター「音と身体の記譜研究」プロジェクト・リーダー)
▶︎チラシ
「リュート・タブラチュアの記譜法を考える——鳴ると記すのあわい」
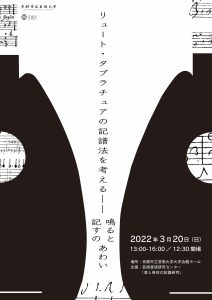
日 時:2022年3月20日(日)開始:13:00/(開場)12:30)
◇ワークショップ:13:00-15:00
◇トーク・セッション:15:15-16:00
会 場:京都市立芸術大学大学会館ホール(京都市西京区大枝沓掛町13-6)ご来場は公共の交通機関をご利用ください。
定 員:50名(一般)一般申し込みはこちらのフォームより申し込みください。(先着順)
参加料:無料・要予約(筆記用具をご持参ください)
主 催:京都市立芸術大学
企 画:京都市立芸術大学芸術資源研究センター 「音と身体の記譜研究」プロジェクト
チラシ(PDF)
▶︎新型コロナウイルス感染防止対策のため,当日受付で検温等に御協力をお願いします。
【概要】
楽譜には、音楽を演奏するにあたっての様々な情報が書き込まれている。この楽譜を書く方法のことを記譜法(ノーテーション)という。
楽譜に書き込まれた情報は演奏をする際に必要なことがらだが、必要なことがらの定義は、地域や文化によって、また同じ地域でも時代によって変わる。
いっけんすると慣習的な読み方で読めるようでも、特定の地域や時代特有の読み方が必要なこともある。また楽譜に書かれていない情報を奏者が読み出すことが必要なことも、奏者によって引き出される情報が異なる場合もある。
ルネサンス期のリュート・タブラチュア(奏法譜)は、文章の句読点に相当する休符が書かれていない。そのため、この時代特有の多声的(ポリフォニック)な音の響き(テクスチュア)も、タブラチュアの表面からすぐには読み取れない。ただ、楽譜に書かれていないことがらを読み出すための読み筋はあり、書かれている情報の背後には、隠されたテクスチュアがある。
記譜法とは、端的に言えば、実際に演奏される音を書き記すための行為であるわけだが、記すという行為と現実に鳴る音とのあいだは、決して直線で結ばれてはいない。
本ワークショップでは、ルネサンス期のリュート・タブラチュアの記譜法を通して、鳴る音と記す行為のあいだを考える。(文:竹内直)
ワークショップ講師:笠原雅仁(古楽器奏者、声楽家)
トークセッション・ゲスト:岡田加津子(作曲家、本学教授)、三島郁(音楽学、本学非常勤講師)
【講師プロフィール】
笠原雅仁(声楽家、古楽器奏者)
武蔵野音楽大学声楽科にて宮本昭太氏に師事。同大学卒業後は有村祐輔氏のもとで声楽、古典音楽理論を学んだ後、1998年に渡英。ロンドンの英国王立音楽大学、大学院古楽科にてN.ロジャース、S.ロバーツの各氏に声楽を、J.リンドベルイ氏にリュートを師事。2002年より仏国のパリ市高等音楽院古楽科にてコルネットをJ.テュベリ氏に師事。2007年にディプロマを取得し、卒業。アンサンブル「エリマ」、「カンパニー・オートルムズュール」など、フランス内外の主要なバロックオーケストラやアンサンブル等と共演、またCDやラジオ・フランス、BBCの為の録音に参加する等、特に初期バロック音楽の専門家として国内外で活躍中。また、パルコ劇場主催の舞台劇「メアリー・ステュアート」にはリュート奏者として出演するなど、様々な分野での活動を拡げている。「アンサンブル・プリンチピ・ヴェネツィアーニ」主宰。
【トークセッション・ゲスト プロフィール】
岡田加津子(作曲家、本学教授)
神戸生まれ。東京藝術大学作曲科卒業、同大学院音楽研究科修了。2003年バロックザール賞、2016年藤堂音楽賞受賞。作曲活動の一方で、楽譜を使わないで音楽する「リズミック・パフォーマンス」のワークショップを全国的に展開。また近年は、バシェの音響彫刻の保存と、音響彫刻を用いた新しい創造活動、教育活動に情熱を注ぐ。京都市立芸術大学教授。京都在住。
三島郁(音楽学、本学非常勤講師)
東京学芸大学大学院修士課程修了後、ケルン大学に留学、大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了。博士(文学)。専門分野は西洋バロック期から19世紀の鍵盤楽器音楽の演奏・作曲論、数字付きバス文化研究。チェンバロ、通奏低音を亀谷喜久子、岩渕恵美子、C. チェラジの各氏に師事。国内外でバロック期の音楽や音楽修辞学などのレクチャーやコンサートを企画・開催。共著に『音楽文化学のすすめ:いまここにある音楽を理解するために』(2007年、ナカニシヤ出版)、『音楽を考える人のための基本文献34』(2017年、アルテス・パブリッシング)他がある。京都市立芸術大学、同志社女子大学、大阪音楽大学、甲南女子大学、大阪教育大学、各非常勤講師、京都市立芸術大学芸術資源研究センター共同研究員。
【トークセッション司会】:滝奈々子(芸術資源研究センター非常勤研究員)
【コーディネーター・進行】:竹内直(芸術資源研究センター非常勤研究員、プロジェクト・リーダー)