アーカイ”バル”ナイトvol.03のお知らせ
アーカイブからアナーカイブへ
ー オーラルヒストリーと記譜研究を振り返る
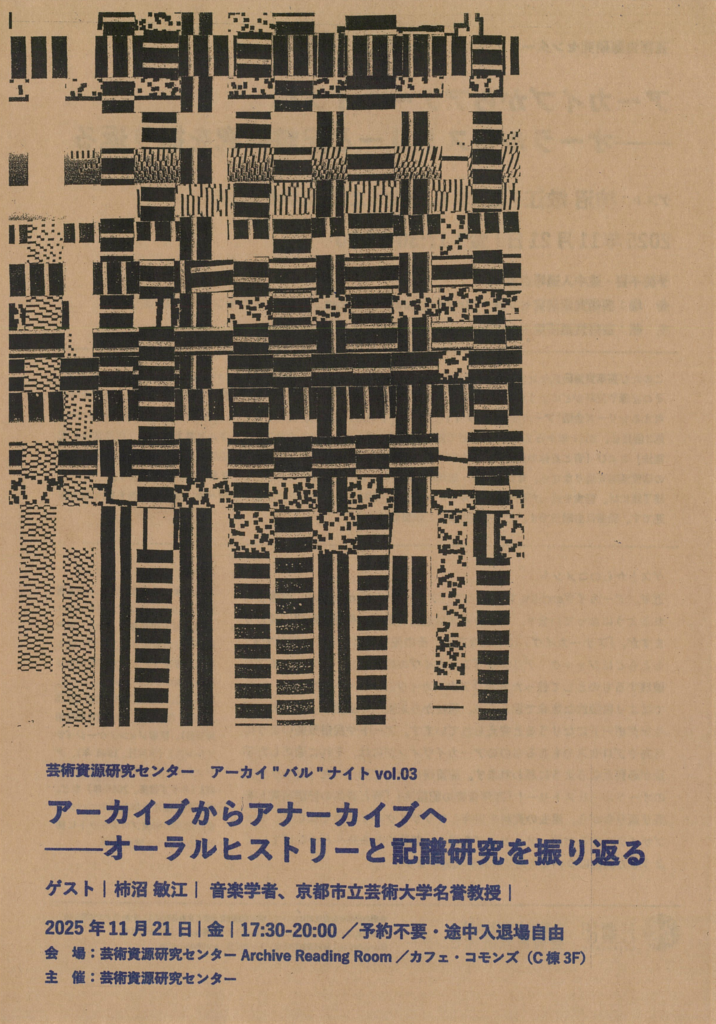
ゲスト:柿沼敏江(音楽学者、京都市立芸術大学名誉教授)
開催日:2025年11月21日(金)17:30〜20:00
会 場:芸術資源研究センター・アーカイブ・リーディング・ルーム/カフェ・コモンズ(ともにC棟3F)
主 催:芸術資源研究センター
チラシ(pdf)
このたび芸術資源研究センターでは、新たに開設された「Archive Reading Room」において、過去の研究活動を振り返り、その記録や資料がどのような芸術資源として存在しうるのか、そして今後どのように保存・活用していくべきかを共に考えるシリーズ企画「アーカイ”バル”ナイト」をスタートいたしました。記憶をたどり、記録を未来へとつなぐ試みです。
第3回目は、2014年から2018年にかけて施されたプロジェクト「フルクサスのオーラルヒストリー」、「西洋音楽の記譜法」および「音と身体の記譜研究」を取り上げ、当時中心となって取り組まれた柿沼敏江先生をお迎えします。先生の研究活動を辿りながら、資料の保存・活用の可能性についてご一緒に考えるひとときとしたいと思います。
終了後には、軽食を囲んだ和やかなバルタイム (会費1,000円)も予定しています。食べ物、飲み物の持ち寄りも大歓迎です。開催は金曜日です。どうぞお気軽にご参加ください。
ゲストからのコメント
近年、アーカイヴarchiveに代わって「アナーカイヴanarchive」が論じられるようになっています。アーカイブは過去の遺産の保存・整理に関わりますが、「アナーカイヴ」はそれを超え、その先を見ようとする概念です。もともとはジャック・デリダが『アーカイヴの病』においてアーカイブを破壊するものとして使った言葉「アナーカイヴ(無アーカイヴ)」は、いまではより積極的な意味で捉えられ、現在から未来へと展開するためのスプリングボードになりうると考えられています。アートや民俗芸能のように行為やプロセスでもあるもののアーカイヴィングには、それに適応した手法が必要となるように思われます。芸資研において関わった「フルクサスのオーラル・ヒストリー」「西洋音楽の記譜法」「音と身体の記譜研究」を振り返りながら、過去の資料を保存してリサイクルするのではなく、アップサイクルする方法、アーカイヴを超え、創造的な未来へとつなげていくような方向性について考えてみたいと思います。
プロフィール
柿沼 敏江(かきぬま としえ)
音楽学者、京都市立芸術大学名誉教授。カリフォルニア大学サンディエゴ校博士課程修了、PhD.専門はアメリカ実験音楽、20-21世紀音楽.著書『アメリカ実験音楽は民族音楽だった』(フィルムアート、2005年)、『〈無調〉の誕生』(音楽之友社、2020年、第30回吉田秀和賞受賞)。訳書ジョン・ケージ『サイレンス』(水声社、1996年)、アレックス・ロス『20世紀を語る音楽』(みすず書房、2010年)など。京都市立芸術大学在職中にバシェ音響彫刻の修復プロジェクトに携わった。バシェ協会顧問。
