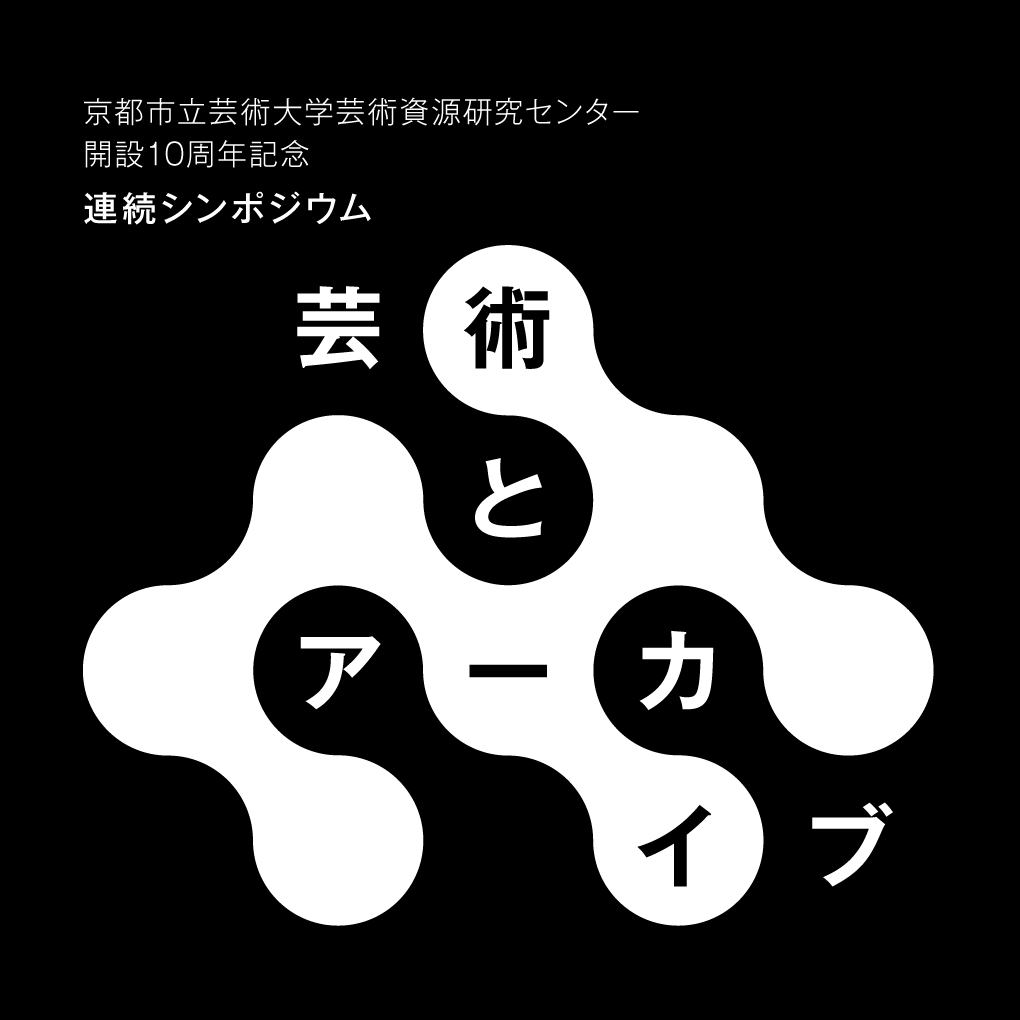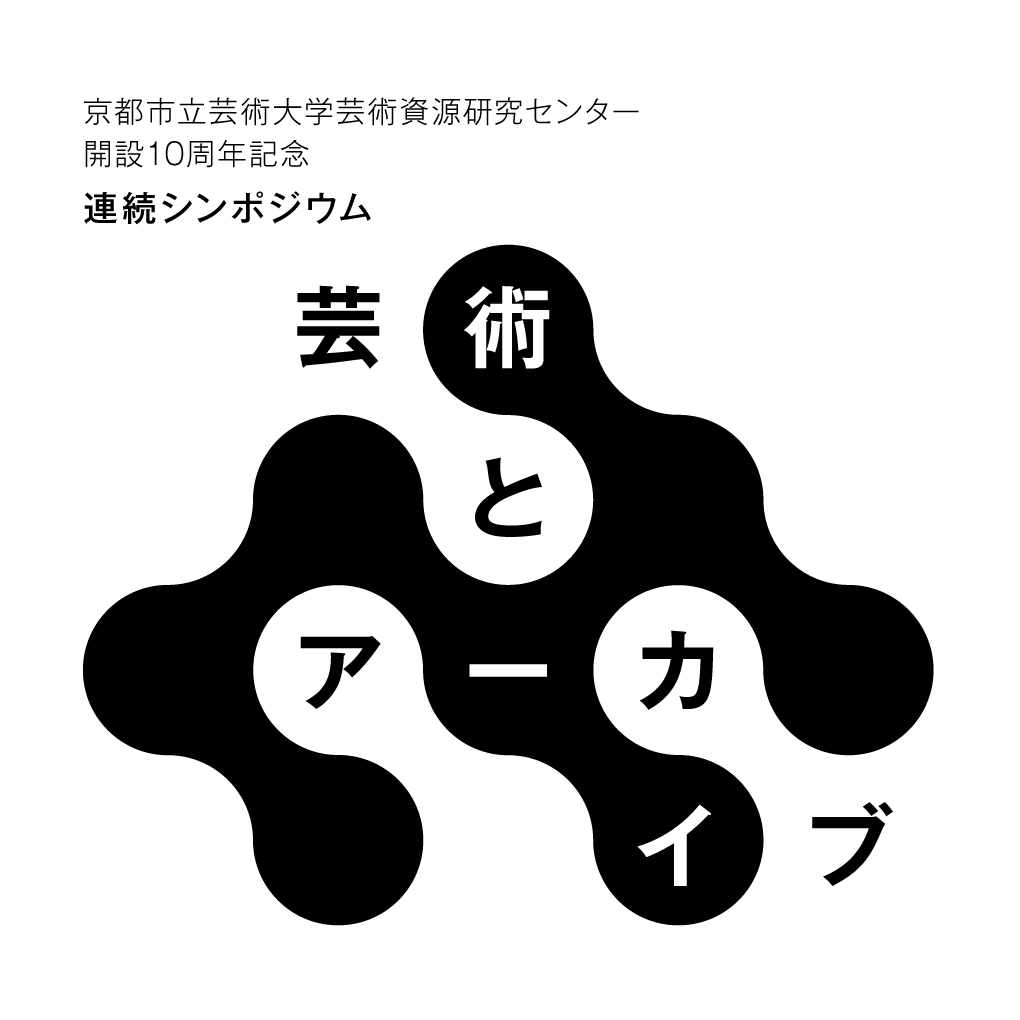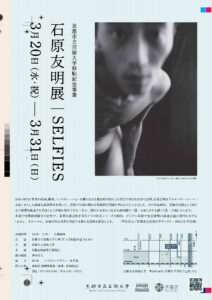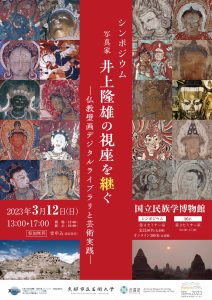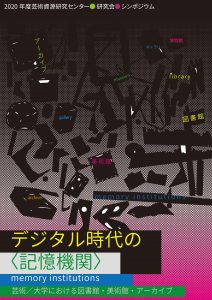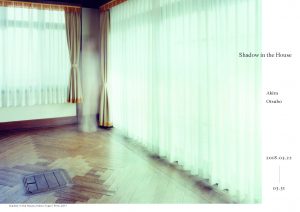京都市立芸術大学芸術資源研究センター 開設10周年記念「ふたたび、芸資研の軌跡を振り返る」
開催日:2025年 3月28日(金)14:00〜16:30チラシ(PDF)
ゲスト:林田新(京都芸術大学アートプロデュース学科准教授、京都市立芸術大学芸術資源研究センター客員研究員)
芸術資源研究センター(略称・芸資研)は、芸術資源の保存・活用を通じて、新たな芸術創造を生み出す「創造のためのアーカイブ」の調査・研究機関として、2014年に開設されました。芸資研のこれまでの10年をふりかえり、ミッションや今後のありかたを考える連続企画《芸術とアーカイブ》♯3として、開設当初の研究員のひとり・林田新氏をお招きし、2部構成で研究会を開催します。
第1部(14:00〜15:00)
第2部(15:10〜16:30)
会場内誘導や座席などについて、特別な配慮を必要とされる方は3月24日までに問い合わせ先までご相談ください。
問い合わせ先:芸術資源研究センター事務局 arc@kcua.ac.jp
2025/03/17
京都市立芸術大学移転記念事業芸術資源研究センター開設10周年記念連続シンポジウム♯2
「アーカイブ」という言葉は、コロナ禍以後、ある活動をいつまでも振り返ることを可能にするものとして流行語になりました。文化芸術の世界でも「アーカイブ」は、過去と現在の活動を未来に伝えるものとして、近年多くの注目を集めています。しかしそもそも「アーカイブ」とは何なのかと問われたら、どうでしょうか。
日 時:2025年2月8日(土)13:00-18:00(12:30開場)アクセス チラシ(PDF)
次 第
挨拶赤松 玉女 (京都市立芸術大学学長・理事長)
開会のおことば(リモート出演)彬子女王殿下 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター特別招聘研究員)
シンポジウム 第1部:芸術にはなぜ「創造のためのアーカイブ」が必要なのか
<登壇者>建畠 晢 (多摩美術大学名誉教授、京都芸術センター館長、元京都市立芸術大学学長)石原 友明 (京都市立芸術大学美術学部名誉教授)柿沼 敏江 (京都市立芸術大学音楽学部名誉教授)佐藤 知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)
|合間|岡田 加津子 (京都市立芸術大学音楽学部教授)渡辺 亮 (パーカッショニスト)
第2部:「芸術とアーカイブ」の未来像
<登壇者>渡部 葉子 (慶應義塾大学ミュージアム・コモンズ副機構長、アート・センター教授)光田 由里 (多摩美術大学アート・アーカイヴ・センター所長・教授)伊村 靖子 (国立新美術館情報資料室室長・主任研究員)平 諭一郎 (東京藝術大学未来創造継承センター准教授)佐藤 知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)
クロージング・スピーチ田中 栄子 (京都市立芸術大学美術学部教授・芸術資源研究センター所長)
問合せ先:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター事務局
2025/01/13
京都市立芸術大学芸術資源研究センター 開設10周年記念
芸術資源研究センター(略称・芸資研)は、芸術資源の保存・活用を通じて、新たな芸術創造を生み出す「創造のためのアーカイブ」の調査・研究機関として、2014年に開設されました。芸資研のこれまでの10年をふりかえり、ミッションや今後のありかたを考える連続シンポジウムを開催します。
初回は、歴代の研究員が集まる研究会のスタイルで、芸資研でおこなわれてきた様々な調査・研究事業をふりかえり、研究者同士でその知見を共有していきます。開設以後10年間におこなわれた、芸術ジャンルや研究分野を横断する数々の取り組みについてのケーススタディから、芸資研が礎としてきた基本理念を再確認することで連続シンポジウムを幕開けします。
#1 研究会「これまで(芸資研は)どうだったのか?」
日時:2024年 12月8日(日)14:00〜17:00
登壇者: 芸術資源研究センター・歴代研究員(以下)前﨑 信也 (京都女子大学 家政学部教授)石谷 治寛 (広島市立大学 芸術学部准教授)高嶋 慈 (京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)竹内 直 (京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)藤岡 洋 (京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)𡌶 美智子 (京都市立芸術大学 芸術資源研究センター)
ディスカッサント:
2024/11/29
令和6年3月をもって退任する美術学部油画専攻の石原友明教授の退任記念企画として「石原友明芸術資源展」を開催いたします。
概要:美術作家石原友明についての芸術資源を、二種類の言説をまとめた「二冊の本」と、その他の関連資料を用いて展示します。これらの本は〈作家自身による〉言説をまとめたものと、美術批評家ら〈作家以外の書き手による〉言説をまとめたものです。そこから浮かびあがる「さまざまな相貌をもつ(あるいはもたされた)複数の作者像」は、ポストモダニズム期の美術作家にふさわしいとも言えますが、同時にそこには、書き手ーメディアによって意図的に切り出され複数化されていく「作家」の像を認めることも可能です。彼と彼以外の作者による二冊の本を軸に、芸術資源としての「言説」の意味について考察しながら、作家石原友明の思考とその創造活動への接近を試みます。
石原友明芸術資源展
関連シンポジウム「もうこれで終わりにしよう。」 アクセス 石原友明 (京都市立芸術大学美術学部油画専攻教授)光田由里 (多摩美術大学アートアーカイヴセンター 所 長・大学院教授)佐藤知久 (京都市立芸術大学芸術資源研究センター教授)岸本光大 (京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA学芸員)
石原友明展「SELFIES」
概要:1980年代に写真や絵画、彫刻、インスタレーションを織り交ぜた複合的手法による作品で注目を浴びて以降、石原友明は「セルフポートレート」をはじめとした多様な表現形式を用いて、芸術や知覚に関わる根源的な問題を明らかにしてきました。その作品群は、芸術が芸術として成り立つ原理を検証する手段として評価を受けてきた一方で、現代や未来につながる身体観や「個」の在り方をも鋭く予見・示唆しています。
チラシ
2024/02/15
「写真家・井上隆雄の視座を継ぐ ―仏教壁画デジタルライブラリと芸術実践―」 井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究 によるシンポジウムが開催されます。
日時:2023年3月12日(土)13:00-17:00シンポジウム参加申請フォーム
【プログラム】
10:00 展示(第3セミナー室)開室
主催:京都市立芸術大学
チラシPDF
シンポジウム要旨集PDF
プロジェクトページ井上隆雄写真資料に基づいたアーカイブの実践研究
2023/02/07
京都市立芸術大学芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル で配信いたします。
▼シンポジウム▼
「デジタル時代の〈記憶機関〉 芸術/大学における図書館・美術館・アーカイブ 」
登壇者:桂英史、佐々木美緒、松山ひとみ、森野彰人(芸術資源研究センター所長・京都市立芸術大学美術学部教授)
■概要
チラシ(PDF)
過去のオンライン配信の様子は芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル でご覧いただけます。
No.29アーカイブ研究会 10月16日(金)18:15-
「デジタル時代の〈記憶機関 memory institutions〉–イントロダクション」
佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター/文化人類学) VIDEO
No.30アーカイブ研究会 10月28日(水)18:00-20:00
「プラットフォームとしての図書館の役割
佐々木美緒(京都精華大学人文学部/図書館情報学・図書館員養成) VIDEO
No.31アーカイブ研究会
「美術館の資料コレクションは誰のもの?」
松山ひとみ(大阪中之島美術館/学芸員・アーキビスト) VIDEO
No.32アーカイブ研究会
「世界劇場モデルを超えて」
桂英史(東京藝術大学大学院映像研究科/メディア研究、図書館情報学) VIDEO
2020/10/12
記譜法研究会企画 シンポジウム&コンサート
糸が紡ぐ音の世界
日時:2019年2月16日(土)14:00~17:00
場所:シンポジウム 京都市立芸術大学 大学会館交流室/コンサート 京都市立芸術大学 大学会館ホール
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
【シンポジウム】
【コンサート】
藤枝守:筝四面による《織・曼荼羅》(委嘱新作)
出演:中川佳代子,丸田美紀,大八木幸恵,渡部志津子(十七弦筝)
2019/01/28
京都市立芸術大学音楽学部教授,芸術資源研究センター所長 柿沼敏江退任記念
フルクサスを語る
日時:2019年1月19日(土)14:00~17:00(13:30開場)
場所:シンポジウム 京都市立芸術大学 大学会館交流室/コンサート 京都市立芸術大学 大学会館ホール
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
【講演】
【シンポジウム】
【コンサート】
アーカイブ研究プロジェクト「フルクサスのオーラル・ヒストリー」
塩見允枝子、一柳慧、靉嘔、エリック・アンデルセン
2018/12/21
Akira Otsubo 「Shadow in the House」 2018年3月22日(木)~31日(土)10:00 – 17:00
会場|京都市立芸術大学 小ギャラリー
主催|京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
企画|高嶋慈
助成|平成29年度 京都市立芸術大学 特別研究助成
チラシ
〈展覧会概要〉
大坪晶の写真作品《Shadow in the House》シリーズは、時代の変遷とともに所有者が入れ替わり、多層的な記憶を持つ家の室内空間を被写体としています。室内に残る歴史の記録であると同時に、ダンサーが動いた身体の軌跡を長時間露光撮影によって「おぼろげな影」として写し込むことで、何かの気配や人がそこにいた痕跡を想像させます。それは、複数の住人の記憶が多重露光的に重なり合い、もはや明確な像を結ぶことのできない記憶の忘却を指し示すとともに、それでもなお困難な想起へと開かれた通路でもあります。
大坪は近年、日本各地に現存する「接収住宅」(第二次世界大戦後のGHQによる占領期に、高級将校とその家族の住居として使用するため、強制的に接収された個人邸宅)を対象とし、精力的なリサーチと撮影を続けています。撮影場所の選定にあたっては、建築史や都市史研究者から提供を受けた論文や資料を参照するとともに、「接収住宅」の所有者の遺族や管理者への聞き取りを行っています。展覧会は、《Shadow in the House》を写真作品、関連資料、資料に基づいた作品、批評テクストからなる複合的なインスタレーションとして構成します。これらを通して、「住宅」という私的空間から大文字の「歴史」や異文化の接触を捉え直す視座を開くとともに、接収の実態や生活様式の変遷が今日の私たちの文化や精神性に与えた影響についても考える機会とします。
また、会期中には、都市史研究者の村上しほり氏と、写真史・視覚文化研究者の林田新氏をお招きしたシンポジウムを開催いたします。
〈関連シンポジウム〉
「記憶⇄記録をつなぐ」Vol.2
2018年3月25日(日)14:00-16:00(参加無料、予約不要)
会場:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
●第一部
アーティストトーク(大坪晶)
レクチャー
「占領下の都市と接収:その記録と記憶」村上しほり(神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 研究員)
「Sujin Memory Bank Project:柳原銀行記念資料館と地域の記憶」林田新(京都造形芸術大学 アートプロデュース学科専任講師)
●第二部
ディスカッション「記憶⇄記録をつなぐ 」
参加者 : 村上しほり、林田新、大坪晶、高嶋慈(京都市立芸術大学 芸術資源研究センター 研究員)
2018/03/07
シンポジウム
「過去の現代の未来2 キュレーションとコンサベーション その原理と倫理」
インディペンデント・キュレーターの遠藤水城の呼びかけにより組織された國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト実行委員会は、2014年に不慮の事故で急逝した國府理による《水中エンジン》(2012)の再制作を試み、これまでに「裏声で歌へ」(栃木・小山市立車屋美術館)、「國府理 水中エンジン redux」(京都・アートスペース虹)での展示を実現しました。この取り組みは、展示を重ねるごとに、現代美術作品の保存・修復や再制作に関連して生じる作品の正当性の根拠、保存対象とすべき物質・現象の理想と現実、再制作過程の記録の重要性とその価値付け、活動記録のアーカイヴの可能性などを問いかける実践ともなり、次第に國府理の《水中エンジン》という具体的で個別の作品の再制作の試みであるのにとどまらない、今日の美術館が取り組むべきより普遍的な課題を明らかにするものともなっています。
日時:2017年11月23日(木・祝)13:30−17:00
場所:兵庫県立美術館 ミュージアムホール(1F)
参加無料(事前申込不要)
タイムスケジュール
13:40~14:40 第1部「國府理《水中エンジン》とキュラトリアルな実践としての再制作」
15:00~16:50 第2部「現代美術の保存修復の責務と倫理」
16:50~17:00 閉会あいさつ 飯尾由貴子(兵庫県立美術館 企画・学芸部門マネージャー)
関連展示
國府理の《水中エンジン》は、剥き出しにした自動車のエンジンを水槽に沈め、水中で稼働させる作品です。國府は、浸水や漏電、部品の劣化などのトラブルに見舞われるたびに、メンテナンスを施して稼働を試み続けました。
日時:2017年11月21日(火)~29日(水)10:00~18:00 ※11月27日(月)は休館日
会場:兵庫県立美術館 アトリエ1(1F)
チラシ
主催:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター、國府理「水中エンジン」再制作プロジェクト実行委員会、兵庫県立美術館
2017/10/10