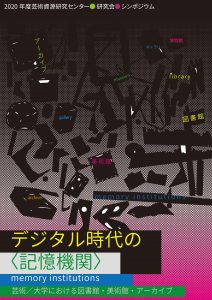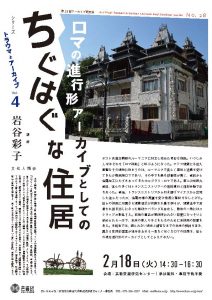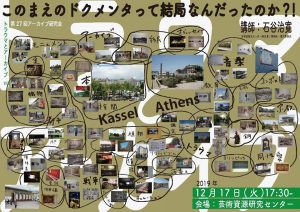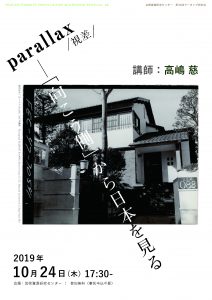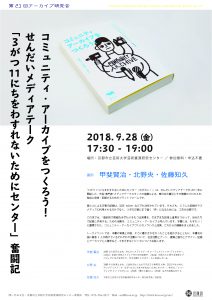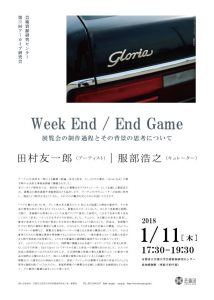京都市立芸術大学芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル で配信いたします。
▼シンポジウム▼
「デジタル時代の〈記憶機関〉 芸術/大学における図書館・美術館・アーカイブ 」
登壇者:桂英史、佐々木美緒、松山ひとみ、森野彰人(芸術資源研究センター所長・京都市立芸術大学美術学部教授)
■概要
チラシ(PDF)
過去のオンライン配信の様子は芸術資源研究センターYou Tubeチャンネル でご覧いただけます。
No.29アーカイブ研究会 10月16日(金)18:15-
「デジタル時代の〈記憶機関 memory institutions〉–イントロダクション」
佐藤知久(京都市立芸術大学芸術資源研究センター/文化人類学) VIDEO
No.30アーカイブ研究会 10月28日(水)18:00-20:00
「プラットフォームとしての図書館の役割
佐々木美緒(京都精華大学人文学部/図書館情報学・図書館員養成) VIDEO
No.31アーカイブ研究会
「美術館の資料コレクションは誰のもの?」
松山ひとみ(大阪中之島美術館/学芸員・アーキビスト) VIDEO
No.32アーカイブ研究会
「世界劇場モデルを超えて」
桂英史(東京藝術大学大学院映像研究科/メディア研究、図書館情報学) VIDEO
2020/10/12
第28回アーカイブ研究会
シリーズ:トラウマとアーカイブvol.4
シリーズ第4回目は,岩谷彩子氏にお話いただきます。
日時:2020年2月18日(火)14:30−16:30
場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
ポスト共産主義期のルーマニアに林立し始めた奇妙な御殿。いつしか人々はそれを「ロマ御殿」と呼ぶようになった。アジア建築にも似た豪奢なその建物に住まうのは、ルーマニアで長らく差別と迫害を受けてきた少数民族ロマであり、その中でも最も移動性が高く、戦前から金属加工にたずさわってきたカルダラリ・ロマである。第二次世界大戦時、彼らの多くはトランスニストリアへの強制連行と強制労働で命を失った。戦後、トランスニストリアから引き揚げマイナスから出発した彼らだったが、金属市場の高騰を受け急速に蓄財をなしとげた。彼らの御殿には異なる建築様式が折衷され富を誇るが、建築途中で放置され剥き出しになった階段やベランダも存在し、敷地の一角にはスクラップが散乱する。家族の遺品が普段使われない部屋にひっそりと納められる一方で、未来の客人や子どもたちのために未使用の部屋もある。本報告では、語られない過去と饒舌なまでの未来の期待を含み、異なる空間的要素が組み合わさる一見ちぐはぐなロマの住居を、彼らの現在進行形のアーカイブとしてとらえてみたい。(岩谷彩子)
■講師プロフィール
シリーズ:トラウマとアーカイブについて
2020/01/20
第27回アーカイブ研究会
シリーズ:トラウマとアーカイブvol.3
シリーズ第三回目は,石谷治寛氏にお話いただきます。
日時:2019年12月17日(火)17:30−
場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
ドクメンタとは5年毎にドイツのカッセルという街で行われている国際芸術展です。今回のアーカイブ研究会では,2017年のドクメンタとは何だったのかをあらためて振り返ります。ドクメンタは,第2次世界大戦中に国が規範にそぐわない近代美術を禁止したことへの反省から,戦後に開始された現代美術展でした。そうした経緯から,表現の自由を象徴する展覧会として,国際的に注目され続けています。2017年に行われた14回目のドクメンタでは,ギリシアのアテネとも共催で,両都市間の連携がなされました。その背景には,ギリシアの文化や思考法が西洋文明にとって重要な規範になってきただけでなく,現在の欧州においても,南と北の経済格差や,地中海を超えて流入する移民など,さまざまな欧州の歴史と現在を照らし出すと考えられたからでした。ドイツーギリシア間とそこから広がる重層的な歴史を主題にした展示物の中には,美術作品や音楽だけでなく,アーカイブ資料の提示も含まれ,パフォーマンスや議論を通して,トラウマ記憶を再演する試みもみられました。本研究会では,さまざまな主題に分けて,全体像を読み解きながら,終了後の論争もふまえて,ドクメンタ14をいま振り返ります。(石谷治寛)
■講師プロフィール
シリーズ:トラウマとアーカイブについて
2019/11/26
第26回アーカイブ研究会
シリーズ:トラウマとアーカイブvol.2
シリーズ第二回目は,高嶋慈氏をお迎えします。
日時:2019年10月24日(木)17:30−
場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
占領期の日本で,将校用家族住宅としてGHQに接収された個人邸宅である「接収住宅」。20世紀初頭の朝鮮半島で,鉄道路線の中継地点として日本人が作った街,大田(テジョン)。植民地期の釜山に住んだ日本人の墓地を土台にし,朝鮮戦争の避難民がバラックを建てて住んだ「峨嵋洞(アミドン)」。日本の中の「アメリカ」と,朝鮮半島の中の「日本」。アーカイブに保存された写真イメージに残る「占領」の記憶。今も人が住む住宅,無人の廃屋,リノベーションされた店舗,再開発が同時進行し,忘却,融合と共存,上書き,転用,そして抹消という複数のレイヤーが共存する空間。批評家として美術作家のリサーチに並走するなかで見えてきた,入れ子状になった「占領」の記憶について,「トラウマ的な負の記憶が堆積する場所」としてのアーカイブと建築物を通して考えます。アメリカ国立公文書館が所蔵する「接収住宅」の写真資料と,韓国の大田に現存する日本家屋や住居の一部となった墓石の事例とともに,アートを通して負の記憶に対峙することの可能性や意義について考えます。合わせて,9月に行った韓国現地レポートも交えてお話しします。 (高嶋慈)
芸術資源研究センターが行う研究会「アーカイブ研究会」では,今年度〈シリーズ:トラウマとアーカイブ〉と題して,連続的な講演と議論の場をもちます。
■講師プロフィール
2019/10/16
第25回アーカイブ研究会
シリーズ:トラウマとアーカイブvol.1
シリーズ第一回目は、作家の裵相順(Bae SangSun)氏をお迎えします。
日時:2019年10月8日(火)17:30−
場所:京都市立芸術大学 芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
芸術資源研究センターが行う研究会「アーカイブ研究会」では,今年度〈シリーズ:トラウマとアーカイブ〉と題して,連続的な講演と議論の場をもちます。
公的な歴史や大きな物語からこぼれおち,それゆえ忘れ去られていく出来事とその記憶については,その記憶を聞きとり,引きうけ,わがこととして受けつぐ試みが,近年多くの場面で行われ,論じられています。
今回考えてみたいのは,忘れ去られつつあり,かつ忘れてはならないと思われるにも関わらず,差別や暴力の経験,負の記憶に結びついているために,あるいは今それについて語ることが新たな暴力や差別を引き起こしかねないために,思い出すことや語ること自体が現在でも困難であるような出来事とその記憶―トラウマ的な記憶―についてです。
たとえば,差別の経験や,国と国のあいまにある中間的な場所の記憶などについては,それについて語る・想起する・言及すること自体が,当事者にとってはもちろん,アーティストや研究者にとってもむずかしいという現状があります。しかしながらだからこそ,そうしたことがらについて語り,聞き,話すための場所が必要だとも言えます。
では実際に,こうした経験と記憶については,どのような試みやアプローチが可能でしょうか。本シリーズでは,記憶をアーカイブする装置としての芸術やフィクションの可能性に注目してみます。集団的というよりも個的な記憶,言語的・歴史的史料というよりも,フィクションや視覚的資料,そしてさまざまな「モノ」などに焦点をあてるこうした実践が,いまどのように可能なのか。異なるフィールドを対象に,忘れられるべきではない経験と記憶についての研究や表現活動を実践してこられた方たちをお迎えし,語ること,想起すること,聞きとり・引きうけ・受けつぐことの可能性とその具体案について,考えてみたいと思います。(芸術資源研究センター教授 佐藤知久)
作家ノート
■講師プロフィール
2019/10/01
第24回アーカイブ研究会
特集展示「鈴木昭男 音と場の探究」をめぐって
日時:2018年12月16日(日)14:00−
場所:京都市立芸術大学 大学会館ホール
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
第24回アーカイブ研究会では、和歌山県立近代美術館で開催された特集展示「鈴木昭男 音と場の探究」(2018年8月4日~10月21日)を企画された奥村一郎氏を講師にお招きします。同展は日本におけるサウンドアートの先駆者である鈴木昭男氏の、1960年代から今日に到る足跡を辿る内容で、チラシやポスター、リーフレットといった印刷物、写真、映像、パフォーマンスで使用した音具などを主要な展示物として構成しました。展示を振り返りながら、今後進める鈴木昭男氏所蔵資料のアーカイブ計画についてもお話いただきます。また、トークとともに鈴木昭男氏によるパフォーマンスをおこないます。
■講師プロフィール
鈴木昭男
2018/11/20
第23回アーカイブ研究会
「日本の録音史(1860年代~1920年代)」
第23回は,音楽学者の細川周平氏をお招きします。
日時:2018年10月11日(木)17:30−19:00
場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
講師は以前、国立民族学博物館にて「植民地主義と録音産業―日本コロムビア外地録音資料の研究」(平成17~18年度科研費)に参加して、録音のアーカイブ化に携わった経験、日本最初の円盤禄音として知られるフレッド・ガイスバーグ録音のCDボックス制作に関わった経験を持つ。今回は日本の初期録音史を振り返り、アーカイブ化の意義について考えます。
■講師プロフィール
2018/10/05
第22回アーカイブ研究会
NETTING AIR FROM THE LOW LAND
第22回は,アーティストの渡部睦子氏をお招きします。
日時:2018年10月4日(木)17:30−19:30
場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
Special Performance by MAMIUMUートークの後にMAMIUMUによるパファオーマンスを予定しております。
チラシ
〈概要〉
約20年に及びオランダをベースにさまざまな土地を移動し、また人に出会いながら「そこにあるもの」を取り込み、独自のユニークな視点で再構成し作品制作を続けてきた渡部睦子。
■講師プロフィール
2018/09/10
第21回アーカイブ研究会
コミュニティ・アーカイブをつくろう!
日時:2018年9月28日(金)17:30−19:30
場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
今年はじめに刊行された、『コミュニティ・アーカイブをつくろう! せんだいメディアテーク「3がつ11にちをわすれないためにセンター」奮闘記』(晶文社)の著者3名によるトークイベントを開催します。
「3がつ11にちをわすれないためにセンター(わすれン!)」は、せんだいメディアテークが2011年に開設した、市民・専門家・メディアテークスタッフの協働による、東日本大震災とその復興のプロセスを、独自に発信・記録するためのプラットフォームです。
個々人による災害の記録は、近年twitterなどでも注目されています。けれども、こうした記録がマスメディアに利用されるだけでなく、つぎの災害にまで届く「声」になるためには、工夫が必要です。
この本では、「個別的で微細な手ざわりをもつ出来事を、さまざまな技術と道具をつかって、自分たちで記録し共有する」ための活動を、コミュニティ・アーカイブと呼んでいます。本書には、わすれン!に蓄積された、コミュニティ・アーカイブづくりのノウハウと成果、これからの課題をまとめました。
トークイベントでは、本書の背景と内容、そこに書ききれなかったことを紹介するとともに、本書刊行後に著者3人が続けているそれぞれの活動について、社会活動とアート、建築と展示とデザイン、記録とアーカイブと人類学など、さまざまなトピックについてお話します。
■講師プロフィール
北野央
佐藤知久
2018/09/10
第20回アーカイブ研究会
「Week End / End Game:展覧会の制作過程とその背景の思考について」
日時:2018年1月11日(木)17:30−19:30
場所:京都市立芸術大学芸術資源研究センター
参加無料(事前申込不要)
チラシ
〈概要〉
■講師プロフィール
服部浩之(キュレーター)
2017/12/24