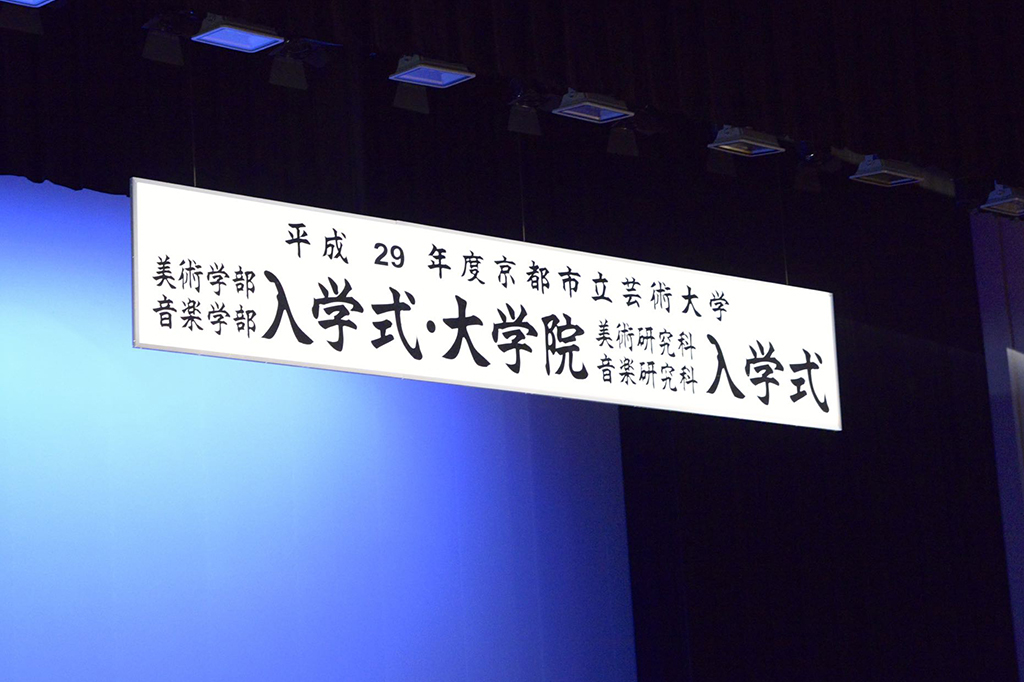![]()
平成29年4月10日,平成29年度京都市立芸術大学入学式を執り行いました。




美術学部135名,音楽学部65名,美術研究科修士課程62名,音楽研究科修士課程25名,美術研究科博士後期課程7名,音楽研究科博士後期課程4名の総計298名が,門川大作京都市長をはじめ来賓の皆様,保護者の皆様,教職員に温かく見守られ,入学式に参加しました。また,開式にあたって,音楽学部在学生が歓迎ファンファーレ「ポール・デュカス作曲 舞踊詩《ラ・ペリ》より」を披露しました。






晴天の下に行われた本年度の入学式,新入生はそれぞれの思いを胸に抱き,期待に満ちた表情が輝く晴々とした顔で参加されていました。
新入生の皆さん,御入学おめでとうございます。
皆様の大学生活が,実りある人生の1ページとなりますように。
教職員一同,心よりお祝い申し上げます。
学長式辞

本日ここに集われた200名の学部生,98名の大学院生のみなさん,入学ならびに進学おめでとうございます。ご臨席いただいたご家族のみなさまにも心よりお祝い申し上げます。また,門川大作京都市長をはじめ,経営審議会,美術教育後援会,音楽教育後援会,美術学部同窓会,音楽学部同窓会のご来賓のみなさまにも,ご臨席いただけましたことに,京都市立芸術大学を代表して深く御礼申し上げます。
今年は桜の開花が例年よりは少しゆっくりしていましたが,そのおかげでちょうど満開の桜の下で,そして洛西の山々がそろそろ新芽を吹きだそうかという頃合いに,みなさんをお迎えできたのはとてもうれしいことです。
さて,みなさんがこれから学ばれるこの京都市立芸術大学は,わが国でもっとも古い歴史をもつ芸術系の大学です。また京都の高等教育機関としてももっとも早く,1880年(明治13年)に創立されました。当初は京都府画学校として設置されましたが,その後すぐに京都市に移管され,以後,京都市画学校,京都市美術学校,京都市絵画専門学校等と改称されていきました。そして戦後,新しい大学制度の下,1950年に京都市立美術大学として発足し,翌々年の1952年には京都市立音楽短期大学も創立され,それらを統合するかたちで1969年にいまの京都市立芸術大学となりました。当時,美術学部は京都・東山の今熊野,音楽学部は岡崎の平安神宮横というふうに学舎は分かれていましたが,創立のちょうど百周年にあたる1980年に,京都・洛西のこの沓掛の地にキャンパスを統合・全面移転し,今日に至っています。
京都市立芸術大学は,制作と作曲・演奏という,実技系中心の大学です。絵やオブジェの制作や,楽曲の創作のみならず,演奏も楽譜という骨に肉をつけることと考えれば,美術も音楽も「つくる」ということが基本にあります。そして「つくる」というのは,現代,人類がその回復をもっとも必要としているものです。そのことの意味を,今日から「つくる」ことの学びを始められるみなさんにここでお伝えしておきたいと思います。
太平洋戦争の終焉からおよそ半世紀後にみなさんは生まれましたが,この半世紀は戦後復興から高度成長を経て,さらには高度消費社会という「豊かな社会」をめざす道程でもありました。「豊かな社会」の行く末には「成熟した社会」が待っているはずでしたが,じっさいには〈貧困〉や〈格差〉など,20世紀には想像もしえなかった語が飛び交う社会に,21世紀に入りわたしたちは直面することになりました。
これは政治や経済の複雑な事情が絡むことがらで,そのあまりの複雑さにわたしたちは茫然とせざるをえないところがありますが,他方で一つ,明確になったことがあります。それは確認するのも悲しいことですが,わたしたちが市民としての力をひどく損なってきたという事実です。
ひとは生きものとして生きるため,生き延びるために,どうしてもしなければならないことがあります。食材を確保すること,食べたあとの排泄物を処理すること,新しく生まれる子どもを取り上げること,育てること,病に苦しむ人を癒すこと,老いゆく人を世話すること,死にゆく人を看取ること,もめ事を仲裁すること,災害に備えること,などなどです。これにはそれぞれ技というものがあって,それを身につけないと生きてゆけない。そういう技が人類の長い歴史のなかで,世代から世代へと伝えられてきました。
20世紀の人類社会は,そのプロフェッショナルを養成し,そういう「いのちの世話」を彼らに委託することで,それらの技をより確実なものにしようとしました。出産や医療や看取りは医師に任せ,介護も専門スタッフに任せ,もめ事の仲裁は役所や弁護士に任せ,災害の備えは自治体や消防署に任せ,というふうにです。人びとはこのように社会のさまざまなシステムに依存するかたちで,「便利」と「快適」を手に入れてきたのです。
そのことで「安心」は得られましたが,そこには一つ,落とし穴がありました。生き延びるためにだれもが身につけなければならないことをシステムに委託することで,わたしたち自身は自分の手でそれをなす力をどんどん失っていったのです。そのことをいやというほど思い知らしめたのが,あの東北での大震災と原発事故でした。災害や事故で社会の基盤が崩れたとき,自分で水や食材を調達することができない,火もおこせない,応急処置や看護もできない……そういう無力を知らされたのでした。「いのちの世話」という,だれもが日々なさねばならないことを,税金やサーヴィス料を払って社会のシステムに委託することを幾世代かにわたりくり返しているうち,みずからそれを担う能力をすっかり失ってしまっていたのです。
もうおわかりかと思いますが,いまわたしたちが回復しなければならないのは,社会が提供してくれるサーヴィスをうまく「消費する」テクニックではなくて,「いのちの世話」を人びとが協力してなす技です。「消費」ではなく,自分たちの手で「つくる」ということです。「つくる」ことの技です。
ここで「つくる」という技は,製品や作品の制作に限られるものではありません。人と人がつながることにも,人と人が協力して何かをなすことにも,あるいは,ここにはないものを想像するにも,別の社会のあり方を構想するにも,そのために何かを調べることにも,そしてさらには危うい所から逃げ出すことにも,技はあります。そしてアートとは技のことです。そういう「生き延びるための技」のもっとも基本的なところを学ぶ場が芸術大学だと,わたしは思っています。
芸術はしかし,物品の製造とは異なります。製造工程を熟知しているだけでは芸術にはなりません。そこには,これまでだれも見たことのないようなものを創りだす「構想力」(imagination)というものが必要となります。
わたしはこの大学に着任してすぐ,学生たちのアトリエをのぞきました。そのとき最初に目にしたのは,大きなキャンバスの前でしゃがみ,ときどき眼を上げはしますがほとんど俯いたままなにか考え込んでいる姿でした。ここはどうするかと迷うだけでなく,きっと,自分はいま何をしようとしているのか,何をしたいのか,何をすべきなのかと考え込んでいたのだと思います。そう,芸術ということで自分は何をしようとしているのか,と。
みなさんもこれからの4年間,きっとこういう光景を何度も目にされると思います。いえ,自身がそういう状態に何度もはまってしまうと思います。芸術が「生き延びる技」であるからには,生きることの意味,在ることの意味,さらには共同生活のあるべき形,他の生きものとの共存の仕方など,考えれば考えるほど,問いは深まり,そして込み入っていかずにはいないからです。
音楽についてこんな問いを発した人がいます。——「音楽で人を殺せるか?」 歌人で演劇家でもあった寺山修司は,音楽がもし人を支え,救うことができるのなら,それで人を殺すことだってできるはずではないかと問いました。芸術は社会の芯にほんとうに届いているか,それができなければ最後まで無害なお飾りで終わるのではないか,命懸けで取り組むというものではなくなるのではないか……と問いを研ぎ澄ましたのです。衝撃でした。どの領域でどのような問いを立てるときも,いつもこれくらい想像力を研ぎ澄ませておかないとだめなんだと思い知らされました。
みなさんもこれから制作や演奏に取り組むなかで,きっと何度も悩むはずです。描けなくなったら,弾けなくなったらどうしようという焦りもあれば,自分には才能も,いやそもそも意欲がないのではないかと考え込むことにもなるでしょう。けれども問いはそのようにみなさんの内側にあるだけでなく,問いを掘り下げていけば,社会のさまざまな困難にも接続していきます。わたしたちは一定の歴史状況の中に生まれ落ちたからです。〈わたし〉が抱え込む問題はかならずどこかで〈社会〉の抱え込む問題につながっているからです。
そのことを知ることで,表現も深まっていきます。感情は自分の内側をほじくることではなく,むしろ時代と向き合う中ではじめて,厚みを得ます。〈わたし〉ではなく〈わたしたち〉が直面している問題にしかと向きあう中で,です。そうしてはじめてあなた方一人ひとりの問いは別の人にも伝わり,やがて多くの人を揺さぶるものともなるのです。
そういう意味で,芸術は果てしのない探究だということになります。教員も同じです。日々同じ探究を続けています。悩み,もがき,苦しんでいます。そして最終的な答えが出るか出ないかもわからない無限の探究であるからには,教員と学生との関係も,どこまでも先輩・後輩の関係です。この探究の前では大家も初心者もありません。問いと向きあうときのセンスや発想が肝心だからです。だから芸術系では教員も,ここをこうしなさいと決めつけるのではなく,「ここんとこ,きついよね」とか「これからどうする?」「ああ,こうくるか?」と横でいっしょに考えるのです。教員にできるのは,問題と格闘する自分の姿を見せるでもなく見せることで,その緊張感と気迫とを伝えることまでです。答えを示すのではなく,取り組み方を伝えるということ。つまりは「薫陶」(香りを染み込ませること)ということです。それがこの大学では少人数教育というかたちで丁寧になされていると,わたしは自信をもって言うことができます。
一人ひとりにも,社会にも,どうにもならないものがあります。それに打ちのめされる体験を反芻しつつ,それでもそこから脱出する一条の光を見つけることが,芸術のいとなみなのでしょう。あるいはこんなふうに言ってもいいかもしれません。人には知らないこと,解決できないことがいっぱいあるけれど,それでもこれは大事,これも大事という余白,そういう余白をまわりに拡げてゆくのが芸術ではないか,と。
そういう余白をもつことが人に勇気を与えます。そしてそういう余白,そういう糊代が,瓦がその端を重ねつつ連なっているように,人びとのあいだで重なりあうあいだは,世界は閉じることなくどこまでも開いたままでありつづけます。
この大学には,「ちょっと助けて」と声を上げれば,だれかがすぐに駆けつけてくれるような,言ってみれば温い気風があります。困ったら,教えてもらう,貸してもらう,直してもらう,手伝ってもらうということが,何の遠慮もなくあたりまえのようにできる空気です。糊代いっぱいのこの空気こそ,ここでは自分は見棄てられていない,孤立してないという安心感を与えてくれるものです。そしてこれは,わたしたちの社会にもっとも必要なものでもあるのです。そしてこの技こそ,物づくりの技以上にたいせつなものではないかと,わたしは思うのです。
みなさんの健闘と幸運を祈ります。
平成29年4月10日 京都市立芸術大学学長 鷲田清一