植松 さやかさん
在学生が、多方面で活躍する卒業生に本学の思い出や現在の活動についてお話を伺う「卒業生インタビュー」。作曲家として活躍中の植松さやかさんへのインタビューをお届けします。
インタビュアーは、音楽学部作曲専攻の門上祥子さんです。
作曲は素直な自分でいられる唯一の場所
音楽との出会いを教えてください。
植松 両親が音楽好きで、幼少期から家の中で様々な音楽を流してくれていました。童謡、クラシック、虫の鳴き声や雷の音などの環境音、松田聖子などのポップスに至るまで多種多様な音楽に囲まれた環境が、音楽への興味を育てるきっかけになっていたと思います。
また、3歳上の姉がヤマハ音楽教室に通い始め、ピアノを弾けるようになったのを見て、私も真似するようになりました。はじめはおもちゃのようなキーボードを与えられたのですが、それを弾くのが楽しかったですね。

植松さやかさん
作曲を始めたのはいつからでしたか?
植松 作曲への興味は、幼稚園の頃から芽生えていたと思います。最初は作曲という意識がなかったため、ただ自由に弾いて終わる遊びのようなものでした。楽譜に結びつけるようになったのは小学2年生の頃で、ヤマハでアンサンブルや創作演奏のコンクールに出るようになってからです。当時は、大まかな知識しか知らなかったので見様見真似で作曲していましたが、中学2年生の頃に専門的に作曲を教えてくれる先生に出会うことができました。コンクールに出す作曲の仕方や和声法を教えていただきながら「この曲はこうできている」とロマン派や近代の作曲家の曲を分かりやすく解説してもらえるのが嬉しくて、月に2回の作曲のレッスンを楽しみに過ごした記憶があります。
京芸を受験しようと思ったきっかけや理由はありますか?
植松 創作演奏のコンクールを受け続けるうちに、音楽を専門的に学びたいという気持ちが強くなり、大阪府立夕陽丘高校音楽科にピアノ専攻生として進学しました。一日に何時間もピアノを練習しなければならない苦労はありましたが、幅広い年代の曲を弾いたり、声楽や器楽の友人の伴奏をしたりするのが楽しかったです。ヴァイオリンの友人には自分が作曲した曲を弾いてもらったり、楽器の仕組みを教えてもらったりしました。また、ピアノの先生に自分が作曲した曲を聴いてもらったときに「スクリャービンみたいだね!」ととても褒めてくださったんです。それが嬉しくて、自分はピアノ専攻ではなく作曲専攻で大学に進みたいという思いが、次第に強くなりました。後から思えば、中高生の自分はいろいろと大変な時期で、作曲は自分の素直な心をそのまま持っていける唯一の場所でした。作曲で音楽の道へ進むことは自然な流れだったのかもしれません。
仲間と音楽を共有できる喜び
京芸の受験はどうでしたか?
植松 なぜかとても楽しく感じました。入試では、同じ場所に集まった受験生同士で「今までどうやって勉強してきた?」と会話したり、6時間の作曲試験を乗り越えた労をねぎらい合ったりしたんですよね。一次試験の4日間だけでも作曲の仲間がいることがとても嬉しかったんだと思います。
作曲を専攻する人ってなかなか少ないですもんね。入学してからの大学生活はどうでしたか?
植松 それが…いきなり自分の実力不足を痛感することになりました。1回生の前期は、順調に作曲専攻に転向でき、対位法のレッスンの進度が周りの人より少しだけ早かったので、自分は作曲専攻生として適応できていると思っていました。しかし、同じ年の秋に行われる試演会で自分の曲が初めて演奏されたとき、一生懸命作曲したにも関わらずとても幼く感じられました。周囲は新しい響きを追求していたのに対し、自分は受験用の型に沿った作曲しかできず、その曲に目新しい響きや発想はどこにもありませんでした。1・2回生の頃は作曲に対して何の自信も持てない状態で、自分には創造力が足りないのではと悩みました。
私も、受験用の作曲がなかなか抜けないことに悩んでいます。どのように脱却されましたか?
植松 自分には知らない音楽が多すぎるので、いろいろな曲を聴かないといけないと思いました。
図書館でCDを借りて、近現代の作曲家の楽譜を見て過ごすことが増えてきました。また松本日之春先生(※元 音楽学部作曲専攻教授、名誉教授)のミュージックコンクレートの作曲レッスンでは、楽器の音以外の音でも音楽の材料にしていくので、選り好みなくあらゆる音と対峙するいいきっかけになりました。そうやって、自分が受け入れられる音楽の幅を広げていったように思います。
どのように脱却するかについてですが、受験の作曲って典型的な展開・型があって要素が一つにまとまるじゃないですか。それでは味付けが濃いので、それぞれの要素を薄くして、別の個性を加えてみたりするのはどうでしょうか。例えば、調性を「複調」にするだけでも、音楽の印象は大きく変わります。また、異なる拍子や不確定な要素を取り入れるのも有効だと思います。即興の部分を設けることでも演奏者に解釈の余地を与え、より多彩な音楽表現が生み出されることがあります。 受験用の作曲で培った「型」が無駄になるわけではありません。美しい和声進行や旋律の重ね合わせ、音色の作りかた、全体をうまくまとめる方法は、「型」を学ぶことで得られると思いますが、大切なのは、その「型」を土台にして新しい表現へと発展させていくことだと思います。
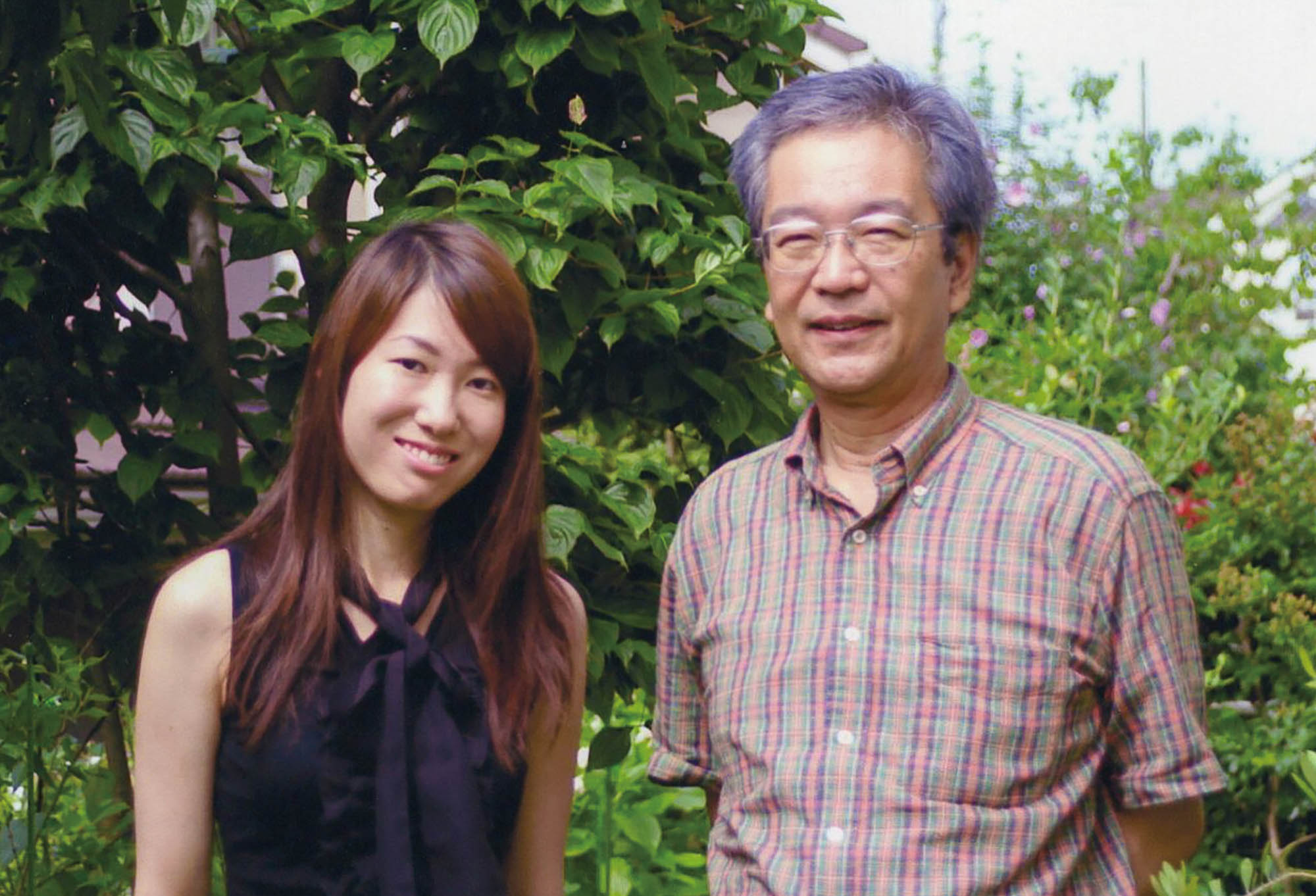
修士時代 松本日之春教授と
1・2回生の頃はなかなかうまくいかなかったと伺いましたが、その後、状況は変わりましたか?
植松 作曲は試行錯誤を繰り返していましたが、編曲を始めたことで私のモチベーションが上がりました。大学に入って器楽専攻の友人がたくさんでき、特に木管五重奏のグループと仲良くなったことがきっかけとなって編曲に携わるようになりました。実際に演奏してもらいながら、各楽器の特徴や音域、得意・不得意な表現などを学び、頭の中で楽器の音色をイメージできるようになりました。
編曲は地道な作業で労力を要するのですが、先輩や友人に頼まれて木管五重奏以外にも弦楽四重奏やオーケストラなどの編曲を任せてもらえるようになりました。この経験のおかげで、次第に作曲への恐怖心が薄れ、音の重ね方や響きの作り方に自信が持てるようになりました。特殊奏法を使わなくても、楽器の特性を活かして豊かな響きを持つ自分のやりたい音楽を生み出せることに気づいたんです。
3回生ではどのような編成の曲に挑戦したのですか?
植松 前期でオーケストラの作曲に挑戦しました。まだ幼さは残っていたものの、自分なりに試行錯誤し、やりたい楽器法に挑戦できました。調性感をぼかしたかった割には和音の響きが強く出てしまって自分の中で葛藤もありましたが、オーケストラの音が充実して響いたときそんなことはどうでもよくなったんです。初めて「自分の曲、ちょっといいかも」と思えたのが、3回生の頃でした。
初めて書き上げたオーケストラ作品について、周りから反応はありましたか?
植松 松本先生から「お前、面白いじゃん」と言われました。「なんか魔法使いの弟子(『ファンタジア』という、クラシック音楽を用いたディズニーの長編アニメーションの中の楽曲)みたいだ」という感想をいただきました。思ってもみなかった言葉で驚きましたが、すごく嬉しかったですね。松本先生のレッスンは、音一つひとつを見るというより、題材は何で全体はどういうプランなのか、それはどの方法なら実現できるのかを考えて音に移し変えていく、そんなレッスンでした。松本先生は試演会のリハーサルにも何度も立ち会ってくださって、どうやって伝えたら自分の望んだ音楽表現になるのか、貴重なアドバイスをたくさんいただきました。作曲者としての在り方を教えていただいたように思っています。
印象に残っている授業はありますか?
植松 和声法や対位法のレッスンでお世話になった前田守一先生(元 音楽学部作曲専攻教授)のレッスンでは、先生が作曲されたオペラなどの作品をたくさん聴かせていただきました。また先輩方が作曲したフーガの楽譜を見せていただき、エクリチュールを重んじる京芸の伝統の上に、今、自分が立っていることを再認識しました。
4回生の頃に受けた中村典子先生(作曲専攻准教授)の楽曲分析も印象深いです。クラスメートがあらゆる曲を持ち寄って、音源を流して意見交換し、それぞれの曲について「これはこういう位置づけの曲だ」とマッピングしていく、とても面白い授業でした。その授業があったからこそ、難しい現代音楽でも他の人と一緒に聴いて、共有できることが楽しいと思えるようになりました。自分一人だけでは気づけなかった視点や解釈を得られたことが、すごく新鮮で嬉しかったです。
修士課程に進まれた理由はなんですか?
植松 学部での4年間を終えても、「まだ勉強が足りない」と感じていました。急に社会に出ることへの不安も大きかったです。でも、松本先生にできるだけ長く師事したかったというのが一番の理由かもしれません。
修士課程では、歌曲や打楽器ソロ、オーケストラの曲等を作曲しましたが、学部生の時には、自分の理解や作曲の技術が足りなくて試すことが出来なかったアイデアも、少しずつ試せるようになってきました。自分にとって、特に歌曲の作曲の相性が良かったようで、今では声楽作品に関わること自体がライフワークになりました。また、松本先生の「音楽はどこにあるか知ってるか?人の心と心の間にあるんだぜ」という、同級生や先輩や後輩と一緒に聞いた松本先生の言葉は、今も自分の音楽の大事な指針になっていると感じています。
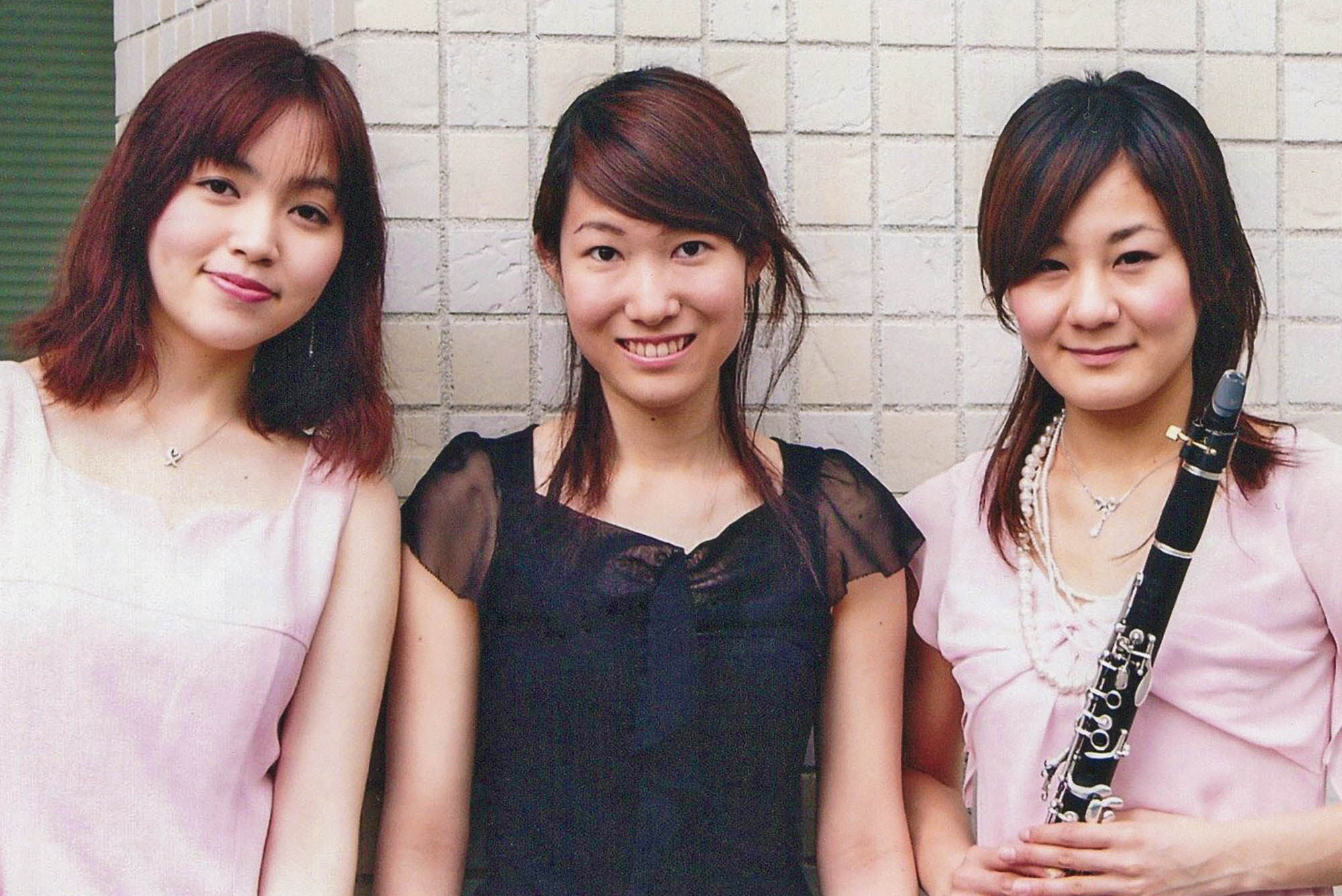
修士時代 「アンサンブルの
夕べ」に出演した演奏者と
「創作・演奏・指導」の三本柱で活動
大学院を修了後、これまでの活動状況をお聞かせください。
植松 25歳で修士課程を修了した後、すぐに神戸山手女子高校と平安女学院大学で授業を担当することになり、翌年から京芸のソルフェージュと和声法の授業も担当するようになりました。日常生活を支える収入はそこから得ることができましたが、作曲の仕事はすぐには安定せず、依頼を受けて曲を書く仕事だけで生計を立てるのは難しかったです。
そのため、編曲の仕事を中心に活動を広げました。オーケストラや合唱の編曲に取り組み、はじめは短い曲の編曲でしたが、次第に「この人はこういう編曲をするんだ」と認知されるようになると、自由度の高い編曲や作曲の依頼が増えていきました。「長浜市民創造オペラ」や「文楽オペラ」(演奏はオーケストラと歌手、演技は文楽人形が担当)を作曲したこともあります。
また、京芸での人のつながりでご縁をいただき、30代からはびわ湖ホール声楽アンサンブルや、びわ湖ホール四大テノールの伴奏をさせていただく機会が増えました。40代になった今は、「創作・演奏・指導」の三本柱で活動することを目標にして、日々過ごしています。

ソルフェージュの授業の様子
印象に残っているお仕事はありますか?
植松 2021年に「長浜市民創造オペラ」から依頼を受けて、80分ほどのオペラを作曲しました。そのオペラの題材が「人柱」だったんです。長浜城を建てる時に、若者が人柱として生き埋めにされたという伝説を元にしています。
重いテーマですね。
植松 ちょうどその頃、母を亡くしたばかりだったんです。自分の家族を失った気持ちと、命を犠牲にする題材を扱うことが重なって辛かったです。メッセージ性は理解していたのですが、心の中ではとても複雑な感情が渦巻いていました。ただ、そんな中で作曲に取り組めたことは、大変ではありましたが何ものにも代えがたい経験でしたし、後々自分の力になったと感じています。
今まで作曲した曲で、一番よくできたと思う曲はありますか?
植松 その長浜のオペラで作曲した曲の中に、歌い手一人とヴァイオリンだけの小さな編成の曲があり、絶望的な内容の曲ですがとても気に入っています。大学生の頃も卒業後も、自分の音の世界を広げたくていろいろな音を盛り込むように音楽を作っていました。でも、その曲では音をそぎ落として、少ない音数でもしっかり成立するものを書けた気がしました。自分が想像した全部の音を、実際に埋め尽くさなくてもいいんだという手応えがありましたね。
音楽には誰かと誰かをつなぐ力がある
今後の活動や夢について教えてください。
植松 まずはやっぱり「その日の授業をきちんとする」とか、「その日やるべき伴奏をしっかりこなす」など、目の前のことを一つずつ積み重ねていくことが大切だと思っています。
そして市民オペラのような作品を作曲して、音楽の経験がない方でも参加できる場を作りたいです。それぞれに役割があって、町おこしのように皆が輝けるような機会をつくることができたら素敵だと思っています。自分の名前を売ることが目的じゃなくて、誰かの役に立ちたいし、自分の音楽が何かをつなぐ存在でありたい。音楽ってそういう力があると思うんですよね。音楽を通じて誰かの人生に少しでも寄り添えるような作品を作っていきたいです。

びわ湖ホール 四大テノールの公演(2024)
素敵な夢ですね。最後に、在学生に向けてメッセージをお願いします。
植松 今、私が教えている学生たちにもいつも伝えていることですが、自分の意見をしっかり持ち、その意見を怖がらずに発信してください。発信の仕方は言葉でもいいし、音楽でもいいので、どんな形でも自分の感じたことや考えたことを外に出せるようになってほしいです。自分の心で何が起こっているかをきちんと感じて、それらをなかったことにせず、自分の音楽や演奏に込められる人になってもらえたらと思います。
受験生へもメッセージをお願いします。
植松 やっぱり、いい経験だけじゃなくて、辛い経験やしんどい経験って、後々自分の力になるんですよね。その瞬間は本当に大変で「なんでこんな思いをしなきゃいけないんだろう」って思うかもしれません。でも、そういう経験があるからこそ、自分の作品や表現に深みが出るし、自分自身も成長できるんです。だから、辛いことがあっても「これは自分を形作る大事なものなんだ」と思って、前に進んでほしいです。

インタビュアー:門上祥子(音楽学部作曲専攻2回生*)
(取材日:2024年11月7日・本学にて)
*取材当時の学年
インタビュー後記

門上祥子(音楽学部作曲専攻2回生*)*取材当時の学年
植松先生にお話をお聞きして自分と重ね合わせるところも多くあり、大変勉強になりました。
今、この大学にてお世話になっている植松先生にも当たり前に学生時代はあったこと、またその経験が必ずしも順調なものではなかったことなど……深く踏み入った質問にも真摯にお答えいただきまして、非常にありがたく思っております。
私自身オペラなどの舞台音楽に興味があったので、植松先生が手掛けられたオペラに関してのお話は特に引き込まれるものでした。卒業後の進路についてのお話も伺うことができたのも良かったです。
この度は貴重な機会をいただきまして、大変ありがとうございました。
(取材日:2024年11月7日・本学にて)
Profile:植松 さやか【うえまつ・さやか】 作曲家

大阪府立夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻を経て、京都市立芸術大学作曲専攻卒業。同大学院修士課程修了。2007年奏楽堂日本歌曲コンクール作曲部門一般の部第3位。オーケストラの編曲や、声楽作品の作編曲に長く携わり、委嘱作品を多数発表している。近年の作曲作品として、2022年に長浜市民創造オペラ《しのぶときく》初演、2025年にメゾソプラノとピアノのためのモノオペラ《羅生門》初演など。現在、創作と演奏の両方で音楽活動を展開している。ソルフェージュや和声法などの指導では、神戸山手女子高校非常勤講師、平安女学院大学嘱託講師を経て、現在京都市立芸術大学非常勤講師として後進の指導にあたっている。びわ湖ホール四大テノール、蓼科カルテット各ピアニスト。大東楽器ピアノ・ソルフェージュ講師。


