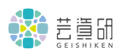フィルムを用いたアート
フィルムを用いたアート(フィルム・ベースド・アート)の歴史を概観すれば,第一次世界大戦後に,幾何学的な図形がリズミカルに動くアニメーションであるハンス・リヒター《リズム24》(1924年)や,多重露光やガラスによる光の屈折などを駆使して現実性が溶解するイメージが綴られるマン・レイ《エマクバキア》(1926年)をはじめとして,ダダやシュルレアリストらの美術家たちが,当時第七芸術と呼ばれた新興芸術である映画を積極的に用い,抽象的で幻想的な表現を探求した。
戦後1947年から1963年にかけてニューヨークの「シネマ16」が,北米での実験映画の展示と流通を行い,スタン・ブラケージ,ジョゼフ・コーネル,ケネス・アンガーなどが知られた。彼らの実験映画は,商業映画と異なる国際的な自主上映のネットワーク網を通じての配給された。他方で,戦後のフランスにおける映像表現としては,ルーマニア出身のイジドール・イズー《涎と永遠についての概論》(1951)が,イメージと音声を分離した編集,フィルムへのスクラッチ,写真フーテージの利用などによって衝撃を与え,つづいてシチュアショニシストのギィ・ドゥボールは,空の画面にナレーションでスペクタクル批判を聞かせる《サドのための絶叫》(1952)や,既製の映像を転用してエッセイを加えた《スペクタクル社会》(1973)などの映画を制作した。米国の西海岸では,写真やオブジェのコラージュを制作した美術家のブルース・コナー《A Movie》(1958)が,既製のフィルム・フーテージを使用したり,フィルムを直接傷つけたり,切り貼りしたり素材を音楽と組み合わせることによって独特の視覚的な効果を生み出し,ミュージック・ビデオの先駆者とも見なされている。1962年から国際的に展開する「フルクサス」に参加したオノ・ヨーコも,身体の部分をクローズアップで拡大して見せる一連の映像を制作した。またベルギー出身のマルセル・ブロータスは1960年代末から,ループする映像の投影をオブジェやテクストと組み合わせたコンセプチュアルなインスタレーション作品を数多く手掛けた。
1960年代から1970年代には,白黒のフィルムのコマが明滅するトニー・コンラッドの《フリッカー》(1965)や45分にわたって空間のズームアップがなされるマイケル・スノウの《波長》(1967)などフィルムや映像の撮影の特性に固有の知覚体験を追求する構造映画と呼ばれる形式も発展した。
1959年に本格的な活動がはじまった草月アートセンターでは,1961年から1971年まで上映会「草月シネマテーク」が開催され,継続的なフィルムを用いた映像の上映活動が行われた。写真家で映像も制作した金坂健二によって「アンダーグラウンド・シネマ」が紹介された。この時期,前衛的なドキュメンタリー映画を制作していた松本俊夫が1960年代になると実験映画にも携わり,また飯村隆彦らは1964年に実験映画制作上映グループ「フィルム・アンデパンダン」を結成して,積極的な活動を行う。1968年に設立されたジャパン・フィルムメーカーズ・コーポラティブが自主上映と配給を行い,後にはイメージフォーラムが実験映画の上映と配給に積極的な役割を担い,活動を継続している。
京都では1968年から美術家たちによって「現代の造形」展が開始され,スライド,フィルム,ヴィデオなどのさまざまなメディアを使った美術作品が展示された。そこには河口龍夫、松本正司、植松奎二、村岡三郎、今井祝雄、山本圭吾、山中信夫、彦坂尚嘉、庄司達、米津茂英、柏原えつとむ、野村仁、植村義夫らが参加した。1972年に京都市美術館で行われた「現代の造形−映像表現’72」では,はじめて日本の美術館において展覧会形式でフィルム作品が展示された。この時期に野村仁は1972年から10年間16mmのカメラを使って1ヶ月に100フィートの日常の映像をコマ撮りし120冊の本に製本する《Photobook》(1972-1982)を制作している。