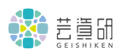初期のコンピュータ(60年 -)
60年代を特徴づける一つの大きな流れとして,アーティストのテクノロジーへの積極的なアプローチが生まれたことが挙げられる。一例として,68年にマサチューセッツ工科大学の学生協同組合の建物内に設置された視覚芸術研究機関CAVS(The Center for Advanced Visual Studies)がある。CAVSでは,ジャック・バーンハム(1931-),ナム・ジュン・パイク(1932-2006)など,後のメディア・アートを牽引する人物がフェローとして所属し,アーティスト自身が助成を受けて研究施設でのエンジニアリングの習得を行い,コンピュータテクノロジーを作品内に導入し,その可能性の模索が為されていた。
また一方で,高度なコンピュータ技術にアクセスのあったエンジニアや研究者などによって作り出されたイメージ群の存在も,この時代における特徴点として挙げられる。研究者らの目的意識は芸術とはなんの関係を持たなくとも,新たな視覚表現として芸術領野から注目を浴びた。例えば,1960年,ボーイング社のエンジニアであったウィリアム・フェッターらが,航空機の設計開発のために用いた作図支援ソフトウェア(CAD)によるコンピュータグラフィックスは,それまでになかった新たな視覚像を世に提示した。
こうした時代背景の中,非常に多くのアーティストやエンジニア,研究者が参加した『サイバネティックセレンディピティ』展(1968, ヤシャ・ライハート企画)や,アーティストとエンジニアが産業界のスポンサーを受けて効率的に共同することを目的とし,ロバート・ラウシェンバーグなども所属していた活動体E.A.T.(Experiments in Art and Technology)など,美術史に残る出来事が生まれた。
この時代のコンピュータを使用した作品は,大型のメインフレームなど,使用されていた機材の専門性の高さから,そのオリジナルは既に失われたものも少なくない。
そのような状況の中,近年の研究では当時のプログラムを,現在のコンピュータ環境を用いて再現する試みも行われている。例えば,60年後半,日本においてコンピュータグラフィックスを駆使してアート作品を作り出し,『サイバネティックセレンディピティ』にも参加していたCTG(Computer Technique Group)の作品はオリジナルとなるコンピュータプログラムが失われている中,近年,その活動のドキュメントアーカイブと共に,現在のプログラム環境を用いた再現・検証プロジェクトが,書籍[i]としてまとめられた。この書籍には,作品の生成プロセスや制御ロジックが事細かに記されている。
[i] 『コンピュータ・アートの創成 CTGの軌跡と思想』(大泉和文, 2015)