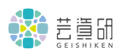コンピュータ・アート
コンピュータを用いて制作された美術作品。1970年代から「コンピュータ・アート」という言葉が使われ、その後マルチメディア・アート、ニューメディア・アート、デジタル・アートなどとも呼ばれる。
マーク・エイドリアン《ランダム》(1963)は、ヨーロッパではじめてコンピュータを使って制作された映像作品である。この時期ジョン・ホイットニーはデジタル映画の領域を切り開いた。彼は、数学の関数や乱数の発生を通して、ヴィジュアル・イメージの変容をコンピュータでの描画を探求した。《Catalog》(1961)といった短編映像はアナログの古い軍事用計算機を用いて制作された。ハンガリーで美術教育を受けたヴェラ・モルナーは、フランスに移住しGRAVの一員としても活躍して幾何学的なパターンの作品を制作していたが,1968年にコンピュータを導入して制作している。Charles Csuri《Hummingbird》(1967年)は,パンチカードを用いるIBM7094コンピュータを使って描画する試みになっている。コンピュータ・アートでは,コンピュータの描画ソフトウェアを使って作成されたいわゆるコンピュータ・グラフィックス・イメージ(CGI)とは異なり,作品を生成するためのアルゴリズムやシステムを通して描画されることが重視され,ジェネラティブ・アートとも呼ばれる。日本では槌屋治紀と幸村真佐男らによって1966年に「CTG(コンピューター・テクニック・グループ)」が結成され,芸術家・科学者らの共同によって,人間と機械の関係を考え直すことが目指された。彼らも参加した1968年にロンドンで行われた「サイバネティック・セレンディピティ」展では,製図機械を用いた画像,光や音の環境,ロボット,コンピュータによって生成された詩などが取り上げられた。テッド・ネルソンによって1960年に設立されたプロジェクト《ザナドゥXandu》は,電子テクストの形式を探求するもので,ハイパーテクスト・システムの先駆けになった。1970年にニューヨークのユダヤ美術館で行われた「ソフトウェア」展でも紹介された。
ジェネラティブ・アートやハイパーテクストなど初期のコンピュータ・アートの試みの多くは,現在のパーソナルコンピューターの環境で使われる情報システムの基盤となるアイデアやイメージの萌芽を生み出した。1970年代以降になると,鑑賞者と電子回路との相互作用を活かしたインタラクティブ・アートや,インタラクションを広域放送や電子通信網を使ってより広げるネットアートが展開していく。1980年前後には業務用アーケード・ゲームや家庭用ゲーム機の普及でコンピュータ・ゲームが身近になっていったが,1980年代から民生のコンピュータの普及とともにコンピュータ・グラフィックスが制作されるようになった。1991年にはキャノン・アートラボが立ち上げられ,招聘されたアーティストとキャノン内部のエンジニアが協同してコンピュータを含むさまざまなテクノロジーが用いられた美術作品が生み出された。石原友明と松井智恵による「ミッション・インビジブル」や中原浩大といった美術家によるテクノロジー・アートの試みから,ダムタイプのメンバーとして活躍していた古橋悌二、また三上晴子による作品などが制作された。