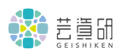ライト・アート
ダン・フレイヴィンは1961年に工業用の電球をモノクロームの絵画の額縁に取り付けるシリーズ《イコン》(1961)を発表し,やがて色のついた工業用の蛍光灯を展示空間に配置していく作風で知られる。また画家ジャスパー・ジョーンズは《フィールド絵画》(1963-64)で,絵画に日用品とともに工業用のネオンをコンバイン(複合)しており,作品の要素として電球や蛍光灯を使用した。
北米西海岸のロバート・アーウィンやジェームズ・タレルらは1967年にロサンゼルス郡立美術館によって行われた感覚遮断の実験を通して,光の知覚に関する関心を深めた。1970年代には光や色の認知と人工照明の制御について科学者との共同実験をともなう「光と空間」の運動が展開した。ブルース・ナウマンも1970年代に蛍光灯をインスタレーションに効果的に用い,1980年代には文字やイメージが時間的に点灯するネオン作品を制作している。現在,トレイシー・エミンをはじめとしてネオンでメッセージを制作する美術作品は一般的になっている。
さまざまな電気部品を組合わせた作品を制作していた宮島達男は1987年に発行ダイオード(LED)を使用しはじめた。LEDは低消費電力で長寿命といった特徴をもつ。1990年代に青色LEDが発明されるまで,白色の電球にとって代わる電球としては普及しなかったが,2000年代に低コスト化の技術開発が進み,一般家庭にも普及するようになった。
1980年代以降もクロード・レベックなど電球を使ったインスタレーションは続けられてきたが,2000年以降にオラファー・エリアソン,カールステン・ヘラーらがこの分野で顕著な活動をはじめたことでライト・アートの再評価は著しい。2013年にパリのグラン・パレで行われた「ダイナモ」展のように,キネティック・アートやライト・アートの再評価と修復や再制作が進められている。
近年の作品は単純なテクノロジーを用いたものから,大量の電球を会場に配し,コンピュータで制御する作品までさまざまである。ラファエル・ロサノ=ヘメル《パルス》(2006)では,天井に取り付けられた300個の電球の点滅は,コンピュータで制御されている。パリで活動するフィリップ・パレーノも,フィルム,彫刻,テクストといったさまざまな素材を用いて展示空間の環境全体を構築する試みを展開しているが,《Marquee》(2006−)では点滅する無数のライトが使われた。暗い空間に光源を付けた鉄道模型が走り,日用品の影が壁面に映し出され,風景が移り変わるクワクボリョウタ《10番目の鑑賞》(2010)のように,動く影絵を使った作品もある。
ライト・アートは,電球という耐久性に限界がある工業製品を素材に用いているために,取り換えの電球が入手不可能になった場合の対処が難しい。移行(マイグレーション)や再解釈によって同じ隠喩的機能をもった電気製品で再制作するといった方策が考えられる。2000年にはダン・フレイヴィンの21点の作品が含まれるパンザ・コレクションのチームが保存・修復のための調査と議論を行った。
また,ネオン・アートは、ケアや修復には訓練を受けた技術者が注意深く扱うべきだとされるが,そもそも保存には適していない。ガスは限られた期間しかもたず,古い電気部品は劣化しやすいからである。保存管理者は,素材を理解すること,状態についての美術家の意図を残し,詳細な記録をとることが推奨され,作品が再制作される場合もある。また展示用のコピーが制作されることもあるが,たとえばブルース・ナウマンは,レプリカに対して次の条件をつけている。1)オリジナルのネオンがまだ存在し動くこと,2)レプリカ作成の前に所有者は貸出に合意すること,3)展示キャプションには展示用コピーであることとオリジナル作品の所有者を明記すること,4)展示終了後にはレプリカを廃棄し,それを写真によって証明しなければならないこと,などである。
参考文献
『万華鏡の視覚:ティッセン・ボルネミッサ現代美術財団コレクションより』森美術館(2009年)